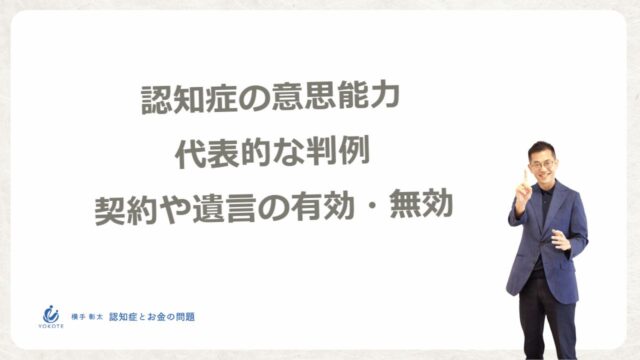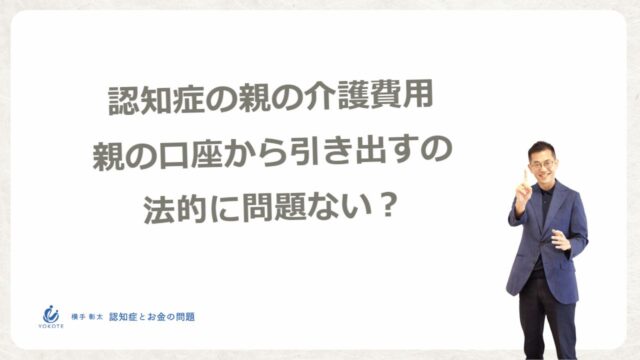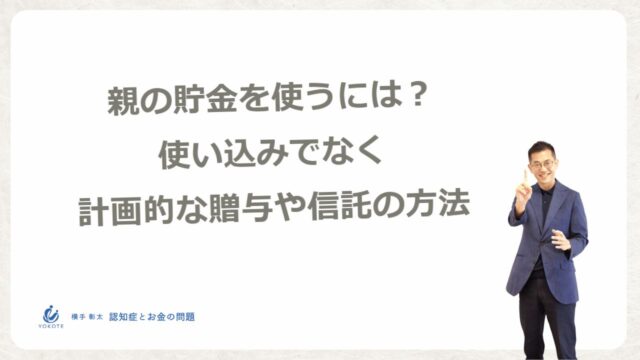代理権とは?親子なら親の代理で契約も預金の移動も何でもできるの?
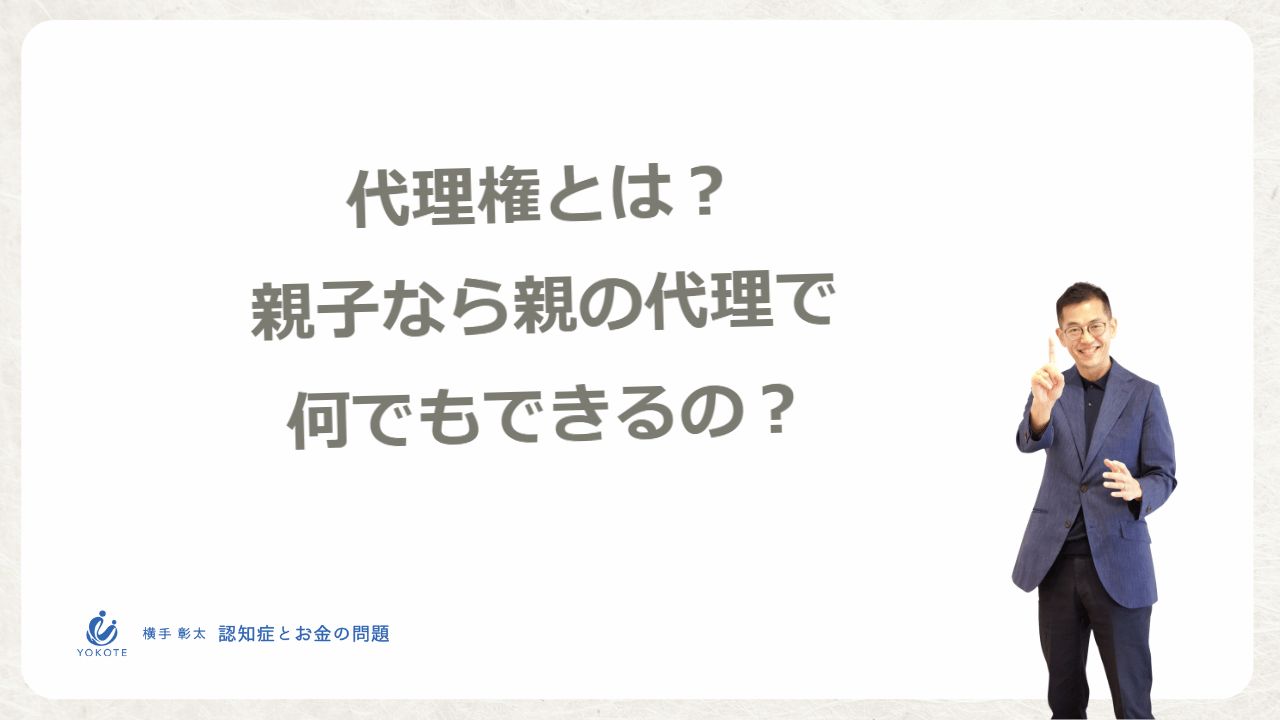
「親の代わりに銀行に行って、お金を下ろすのは問題ないですよね?」
私、横手はこのような質問を本当によくいただきます。
親が高齢になり、通帳や契約書を扱うのが難しくなってくると、「親子なんだから代理でやっても大丈夫」と思うのは自然なことです。
しかし、法律の世界では親子だからという理由で自動的に代理権が与えられるわけではありません。
民法上の「代理権」とは、他人に代わって法律行為を行う正式な権限のこと。
この権限がないまま契約や出金を行うと、たとえ親のためであっても「無権代理」とされ、トラブルの原因になります。
この記事では、家族信託コンサルタントの私・横手彰太が、法律上の代理権とは何か、親子間でどこまでできるのか、そして認知症に備えてどのように“正しい代理権”を整えるべきかを、専門的な立場からわかりやすく解説します。
この記事の筆者
認知症とお金の専門家・横手彰太。これまでに家族信託の締結サポートは累計350組以上、信託財産総額180億円超を担当してきました。
日本全国67ヶ所の公証役場での手続き実績があり、NHK「クローズアップ現代+」やAERA、プレジデント、日本経済新聞など多数メディアでも紹介されています。セミナー講師としても300回以上登壇し、一般のご家庭から税理士、不動産会社まで幅広い方々にお金と認知症対策について解説してきました。著書に『親が認知症になる前に知っておきたいお金の話』をはじめ計5冊があります。

親が認知症になると、財産管理や相続の問題が一気に複雑化します。
だからこそ、「備えるなら今」が大切です。親に認知症の症状がある場合はすぐに対策しないと後悔しますので無料相談をお申し込みください。家族信託を詳しく学びたい方は2時間以上の濃い内容で解説した特別YouTube動画もご案内していますので、ぜひ最後までご覧ください。
認知症とお金の問題は、本当に重要な問題です。
手遅れになる前に、しっかりと考えて行動しましょう。
「親のために」は、法律では通らない
私、横手はこれまで数多くのご家族から「親が高齢で銀行や役所の手続きが難しくなったので、私が代わりにやっています」というお話を聞いてきました。
しかし、その多くのケースで「親子だから問題ない」と思い込んでいるのが実情です。
日本の法律では、たとえ親子や配偶者であっても、自動的に相手の代理人になれるわけではありません。
親の通帳からお金を引き出したり、不動産の契約を代わりに結んだりする行為には、明確な代理権(だいりけん)が必要です。
代理権とは、本人に代わって法律上の行為を行う権限のこと。
民法第99条には、「代理人のした行為は本人に対して直接その効力を生ずる」と規定されていますが、それは「正しい代理権を持っている場合」に限られます。
つまり、「親のためだから」「頼まれたから」という理由だけでは、法律的には通用しないのです。
ここを誤解したまま行動してしまうと、後々トラブルや法的責任を問われる可能性があります。
法律上の「代理権」とは何か
代理権とは、他人の代わりに契約や手続きを行うための法的な権限を意味します。
代表的なものに、「委任契約による代理」「法定代理」「任意後見契約による代理」などがあります。
| 種類 | 内容 | 例 |
|---|---|---|
| 委任による代理 | 本人が信頼できる人に任せる契約 | 親が子に「この手続きを代わりにやって」と依頼し、委任状を交わす |
| 法定代理 | 法律によって自動的に代理権が与えられる | 親権者が未成年の子の代理をする場合など |
| 任意後見契約による代理 | 将来の判断能力低下に備えてあらかじめ契約を結ぶ | 認知症に備えて親が子に後見人を任せる場合 |
つまり、「代理人」として行動するためには、本人が委任するか、法律に基づいた立場である必要があります。
親子関係や夫婦関係は法律上の「信頼関係」ではありますが、「代理権の根拠」にはなりません。
親子でも「無断で代理」はできない
親がまだ判断能力を保っている場合、本人の署名・押印・意思確認があれば、委任状を作成して子どもが代わりに手続きを行うことは可能です。
しかし、認知症などで意思確認が難しくなると、その委任状は効力を失います。
たとえば、次のようなケースを考えてみましょう。
| ケース | 結果 | 理由 |
|---|---|---|
| 親が委任状を書き、明確な意思を確認できる | 有効 | 本人の同意に基づく代理 |
| 親が認知症で判断能力を失っている | 無効 | 意思能力がないため契約が成立しない |
| 子が親のために通帳から出金 | 違法の可能性 | 正当な代理権がないため不正出金とみなされる場合も |
このように、親が認知症になると、形式的に委任状を作っても意味がなくなります。
「親が頼んでいたから」という善意があっても、法律上は無権代理(むけんだいり)とされ、場合によっては無効や損害賠償の対象になることもあります。
認知症で「代理できなくなる」最大の問題
私、横手は現場で何度も「親が認知症になってから手続きが止まった」というご相談を受けてきました。
たとえば、施設入居費の支払いのために不動産を売却したいのに、契約書に親の署名ができない。
銀行に行っても、「お母さまご本人でなければ出金できません」と言われ、生活費すら引き出せない。
これは、認知症の発症によって「代理権を与える契約」自体ができなくなるためです。
法律上の行為には「意思能力」が必要であり、判断力がなくなった状態では代理契約も委任も成立しません。
つまり、認知症になると、家族が代理として動ける仕組みが完全に途絶えるのです。
ここに、後見制度や家族信託が必要とされる理由があります。
「親子の信頼関係」ではなく「法的根拠」が必要
多くの家族は、「親のために動いているのだから問題ない」と感じています。
しかし、法律の世界では「気持ち」ではなく「根拠」が重視されます。
親子関係があっても、銀行や不動産登記などの場面では、必ず代理権の証明が求められます。
そのため、あらかじめ法的に有効な代理権を準備しておくことが欠かせません。
私、横手は現場で「感情の信頼関係と法的な信頼関係は別物です」とお伝えしています。
家族の信頼を法的に形にする――それが、家族信託や任意後見契約の本来の役割なのです。
家族信託と任意後見契約で「合法的な代理権」を持つ
では、どうすれば親のために安心して代理行為を行えるのでしょうか。
代表的な方法は「家族信託」と「任意後見契約」です。
家族信託では、親(委託者)が信頼できる子ども(受託者)に財産を託すことで、法律上の管理・運用・処分の権限が移ります。
そのため、親が認知症になっても、受託者が契約や出金などを代わりに行うことができます。
任意後見契約は、将来の判断能力低下に備えて、親があらかじめ後見人(子どもなど)を指定しておく仕組みです。
家庭裁判所に任意後見監督人が選任されると、正式な代理権が発生します。
| 項目 | 家族信託 | 任意後見契約 |
|---|---|---|
| 契約時期 | 判断能力があるうちに | 判断能力があるうちに |
| 効力発生 | 契約直後 | 判断能力が低下した後 |
| 主な権限 | 財産管理・処分・運用 | 生活・医療・介護などの代理 |
| 裁判所の関与 | 不要 | 必要(監督人選任) |
私、横手は実務上、両者を「生前の財産管理と生活支援の両輪」として組み合わせることを推奨しています。
家族信託でお金の流れを止めず、任意後見で生活や医療の安心を確保する――それが、認知症時代の最も現実的な備え方です。
「親子だからできる」ではなく「仕組みを作るからできる」
親のために何かをしてあげたいと思う気持ちは、すべての家族に共通するものです。
しかし、法的な仕組みを知らずに行動してしまうと、その善意がトラブルの原因になることもあります。
私、横手は「親子だからできること」ではなく、「きちんとした仕組みを作るからできること」に変えていくべきだと考えています。
代理権を正しく理解し、法的根拠のある行動をとることで、家族の信頼関係を“法律で守る”ことができるのです。