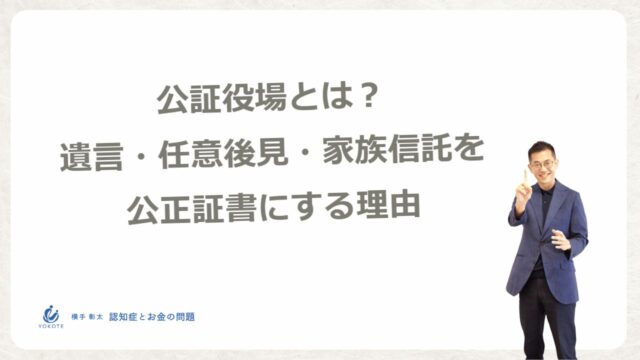英語圏での認知症と財産・資産運用・相続はどうなっている?
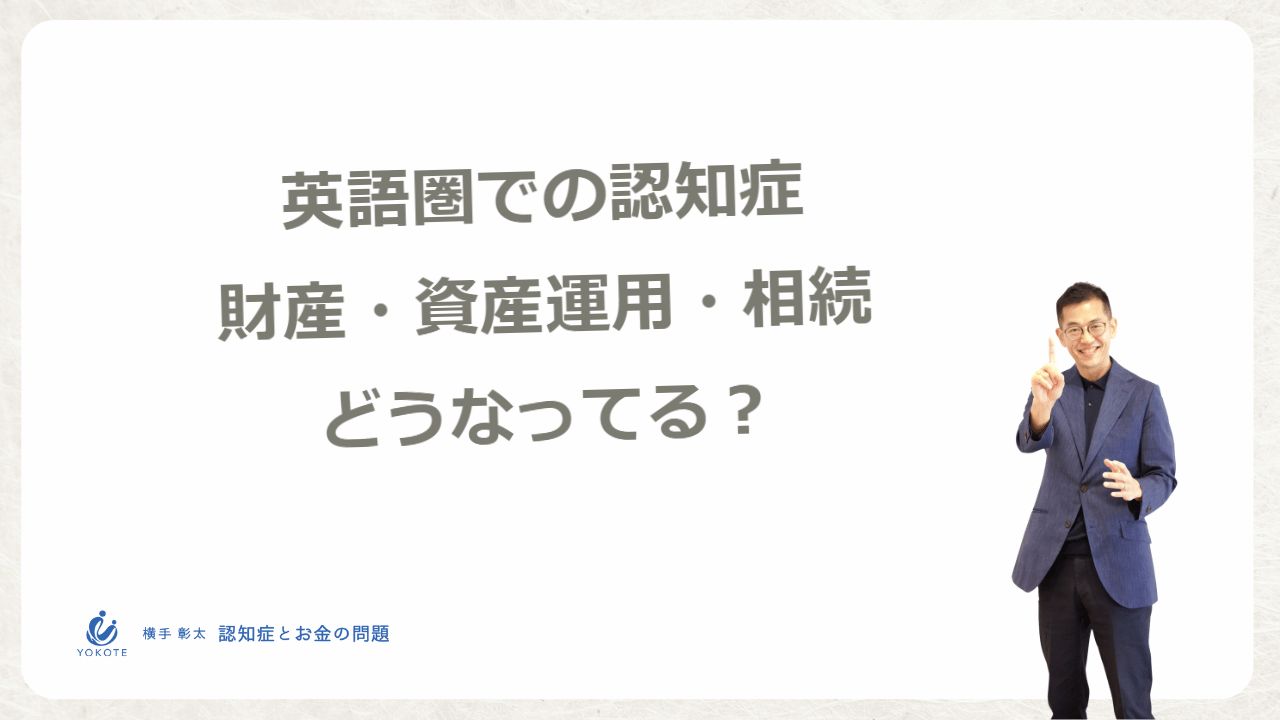
日本では高齢化の進展に伴い、認知症を発症する方が増加しています。特に親が認知症になる前に、財産の管理や相続対策をどうするかは多くの家庭で大きな関心事です。家族信託コンサルタントの横手彰太さんも、これまで数多くの相談に対応し、家族信託や生前贈与を用いた解決策を提案してきました。その経験の中で「日本ではまだ制度が整いきっていない部分もあるが、海外ではどうしているのか」と疑問を持つ方も少なくありません。
この記事では英語圏の制度を紹介しながら、日本の現状との比較を通じて、読者の判断材料となる視点をお伝えします。
この記事の筆者
認知症とお金の専門家・横手彰太。これまでに家族信託の締結サポートは累計350組以上、信託財産総額180億円超を担当してきました。
日本全国67ヶ所の公証役場での手続き実績があり、NHK「クローズアップ現代+」やAERA、プレジデント、日本経済新聞など多数メディアでも紹介されています。セミナー講師としても300回以上登壇し、一般のご家庭から税理士、不動産会社まで幅広い方々にお金と認知症対策について解説してきました。著書に『親が認知症になる前に知っておきたいお金の話』をはじめ計5冊があります。

親が認知症になると、財産管理や相続の問題が一気に複雑化します。
だからこそ、「備えるなら今」が大切です。親に認知症の症状がある場合はすぐに対策しないと後悔しますので無料相談をお申し込みください。家族信託を詳しく学びたい方は2時間以上の濃い内容で解説した特別YouTube動画もご案内していますので、ぜひ最後までご覧ください。
認知症とお金の問題は、本当に重要な問題です。
手遅れになる前に、しっかりと考えて行動しましょう。
英語圏での認知症と財産管理の仕組み
イギリスやアメリカでは、認知症など意思能力を失う可能性に備えて「後見制度」や「代理権契約」が広く普及しています。
代表的な仕組みがイギリスの「Lasting Power of Attorney(LPA)」、アメリカの「Durable Power of Attorney(DPOA)」です。これらは本人がまだ判断能力のあるうちに、信頼できる家族や専門家を代理人として指名し、将来に備えて財産や医療の意思決定を任せられる契約です。制度上は本人の希望が重視され、柔軟に運用できる点が特徴です。
| 項目 | イギリス:LPA | アメリカ:DPOA | 日本:成年後見制度 |
|---|---|---|---|
| 制度の目的 | 判断力を失ったときに備えて、信頼できる代理人に財産管理や医療判断を委ねる | 判断力喪失後も有効な代理権契約として、財産や法律行為を継続して代理可能にする | 認知症などで判断能力を失った人の財産を、家庭裁判所が選任した後見人が管理 |
| 主な対象分野 | 財産・金融、健康・福祉の2種類を選択・併用可能 | 主に財産・金融の代理権、州によって医療意思決定も可能 | 財産管理、身上監護(生活・医療など) |
| 開始のタイミング | 本人が意思能力を持つ間に作成し、裁判所登録後に効力発生 | 本人が意思能力のあるうちに作成、判断力喪失後も効力が継続 | 判断能力が低下してから、家庭裁判所が後見人を選任して開始 |
| 代理人の選任 | 本人が自由に選べる | 本人が自由に選べる | 裁判所が決定(家族が選ばれるとは限らない) |
| 費用の目安 | 登録費用:約82ポンド(約1万5千円)×書類ごと、弁護士に依頼すると数万円〜10万円程度 | 州ごとに異なるが、公証人手数料や弁護士費用で数百ドル程度、比較的低コスト | 申立費用2〜3万円+鑑定費用5〜10万円、後見人への報酬が月2〜6万円かかる場合あり |
| 本人意思の尊重 | 高い。本人の指示を文書に残せる | 高い。契約書で詳細に権限を設定可能 | 制度上は本人の利益優先だが、裁判所の判断が強く反映される |
| 柔軟性 | 高い(利用目的に応じて設計可能) | 高い(権限を細かく設定可能) | 低い(裁判所の監督が強く、自由度が乏しい) |
このように比較すると、LPAやDPOAは本人が元気なうちに「誰に、どのような権限を任せるか」を自由に決められるのに対し、日本の成年後見制度は裁判所主導であり、費用も継続的にかかる点が大きな違いです。そのため日本では、私の提案している「家族信託」を活用することで、海外の制度に近い柔軟性を持たせることができます。
イギリスの「Lasting Power of Attorney(LPA)」とは?
イギリスの「Lasting Power of Attorney(LPA)」は、将来認知症などで判断力を失った場合に備えて、あらかじめ信頼できる人に財産管理や医療・介護に関する意思決定を任せられる制度です。本人がまだ意思能力を保っているうちに作成し、家庭裁判所の登録を経て効力を持ちます。LPAには財産・金融を扱うものと、健康・福祉に関するものの二種類があり、必要に応じて選択や併用が可能です。本人の希望を尊重しつつ柔軟に運用できる点が特徴で、日本の成年後見制度よりも自由度が高く、英国内では広く普及しています。
アメリカの「Durable Power of Attorney(DPOA)」とは?
アメリカの「Durable Power of Attorney(DPOA)」は、本人が病気や認知症などで判断力を失っても効力が継続する代理権契約です。通常の委任契約(Power of Attorney)は本人が判断できなくなると失効しますが、DPOAは「Durable=持続的」という特性により代理人の権限が存続します。財産の管理や契約行為、銀行口座の操作など幅広い権限を委ねることができ、本人が元気なうちに作成しておく必要があります。州ごとにルールは異なりますが、裁判所を介さずに柔軟な財産管理を続けられる点が特徴で、日本の成年後見制度に比べて自由度が高い仕組みといえます。
日本の成年後見制度とは?
日本の成年後見制度は、裁判所の関与が強く、支出の自由度も限定されがちです。私、横手が提案する「家族信託」が注目される理由は、こうした硬直性を避け、本人や家族の希望を反映しやすい仕組みだからです。海外の事例を見ても、日本における家族信託の活用は、国際的な潮流と重なる部分があるといえるでしょう。
認知症と資産運用の考え方の違い
英語圏では、認知症を前提とした資産運用は「トラスト(信託)」と密接に関わっています。特にアメリカでは、リビングトラスト(生前信託)が広く利用され、本人が認知症などで判断力を失った後も、あらかじめ指定された受託者が資産を運用・管理できます。資産の承継や運用を途切れさせない点で、日本の家族信託とほぼ同じ発想です。
一方、日本では金融機関の口座凍結や後見制度の制約があるため、運用の自由度が低くなりがちです。私横手が繰り返し発信しているのは、「親が元気なうちに仕組みを作ること」が重要だという点です。
海外と同様に、日本でも早めの準備こそが柔軟な資産運用を可能にします。
相続と遺産分割における文化的な違い
相続についても英語圏と日本では違いが見られます。
アメリカやイギリスでは、本人の意思を尊重する遺言(Will)が基本であり、遺言の効力は非常に強いとされています。遺留分制度のように、必ず一定割合を家族に残さなければならないルールは存在しません。そのため「どの資産を誰に残すか」を本人が自由に決められることが多く、信託や遺言を組み合わせて資産承継が設計されます。
日本では遺留分が法的に保障されているため、相続人全員の権利を調整する必要が生じます。この違いが、相続トラブルの発生要因にもなっています。家族信託や遺言を通じて「親世代の意思をいかに尊重するか」を重視しており、海外の自由度と比較することで、日本における制度設計の工夫の必要性がより浮かび上がります。
日本と英語圏の制度比較表
| 項目 | 日本 | 英語圏(米・英) |
|---|---|---|
| 認知症時の財産管理 | 成年後見制度(裁判所の監督下) | LPA / DPOA(本人が任意で代理人指定) |
| 資産運用 | 制約が多く柔軟性に欠ける | リビングトラストで継続可能 |
| 相続制度 | 遺留分制度があり、相続人間の調整が必要 | 遺言の自由度が高く、本人意思が優先 |
| 主流の仕組み | 家族信託が注目される段階 | 信託(トラスト)が制度として定着 |
伝えたいこと
私、横手は自身のコンサルティングやYouTubeで「制度の違いに目を向けることで、日本においても家族に合った対策を取れる」という考えを繰り返し強調しています。海外の事例は決してそのまま日本で使えるわけではありませんが、先行する仕組みから学ぶことは多いといえます。
特に「意思能力を失う前に仕組みを整えておくこと」の重要性は、日本でも共通して当てはまる原則です。
まとめ
英語圏では、認知症に備えた財産管理や相続制度が整備され、本人の意思を尊重した仕組みが一般的に活用されています。日本では成年後見制度の限界から、家族信託が新しい選択肢として注目されています。横手彰太さんの実践から見えてくるのは、海外の仕組みを参考にしつつ、日本においても家族ごとに最適な方法を選ぶことの大切さです。親が認知症になる前に準備を進めることで、財産や生活の安心を守る道が開けます。