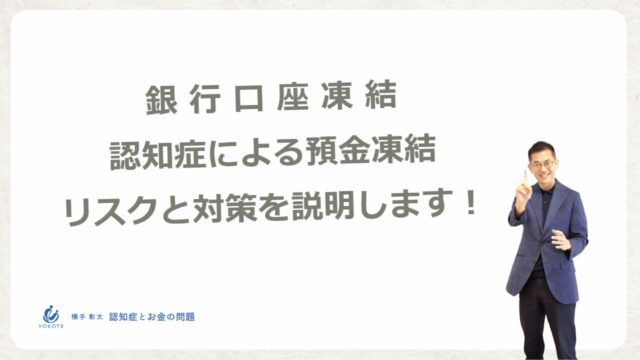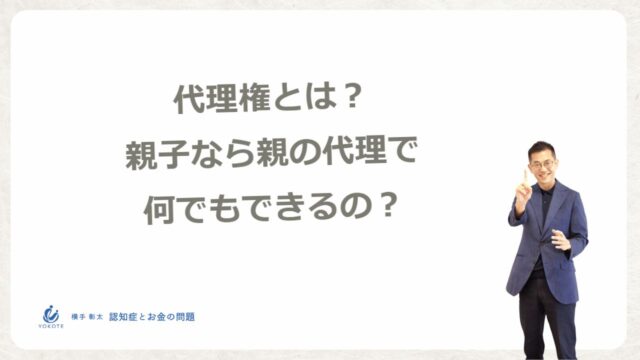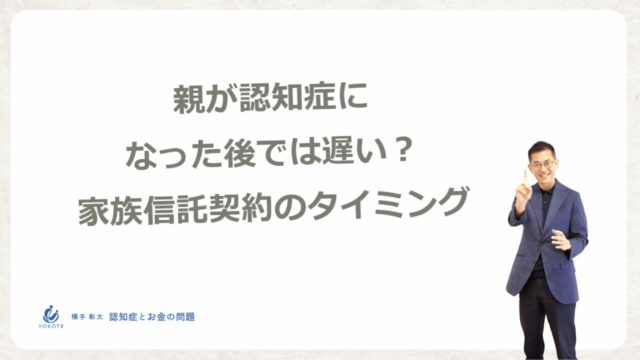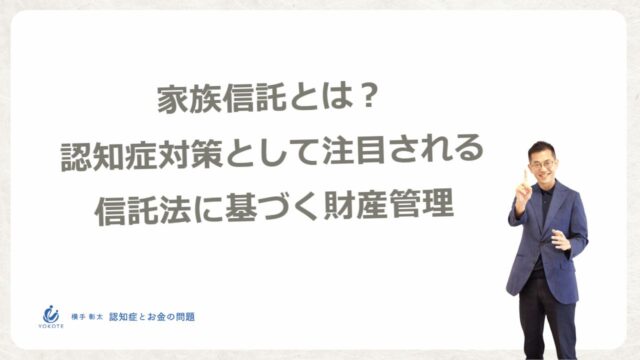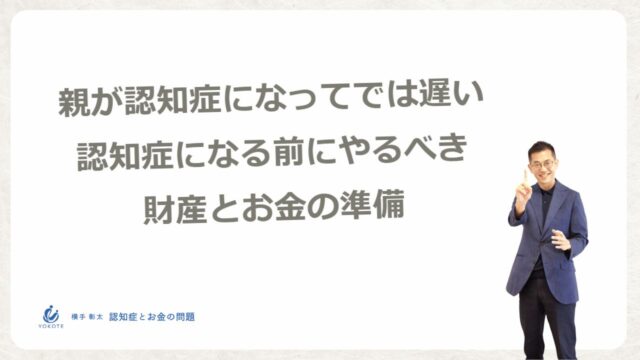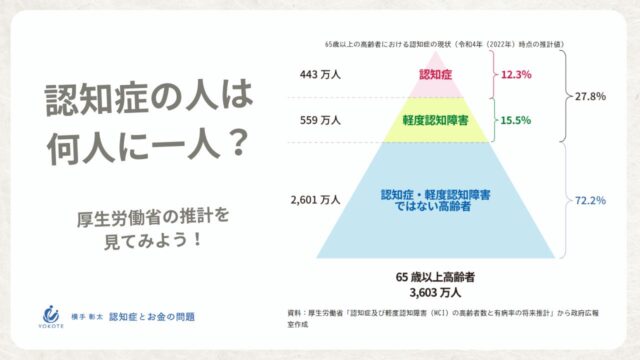人生会議とは?遺言書や医療・ケアの希望より認知症のことを
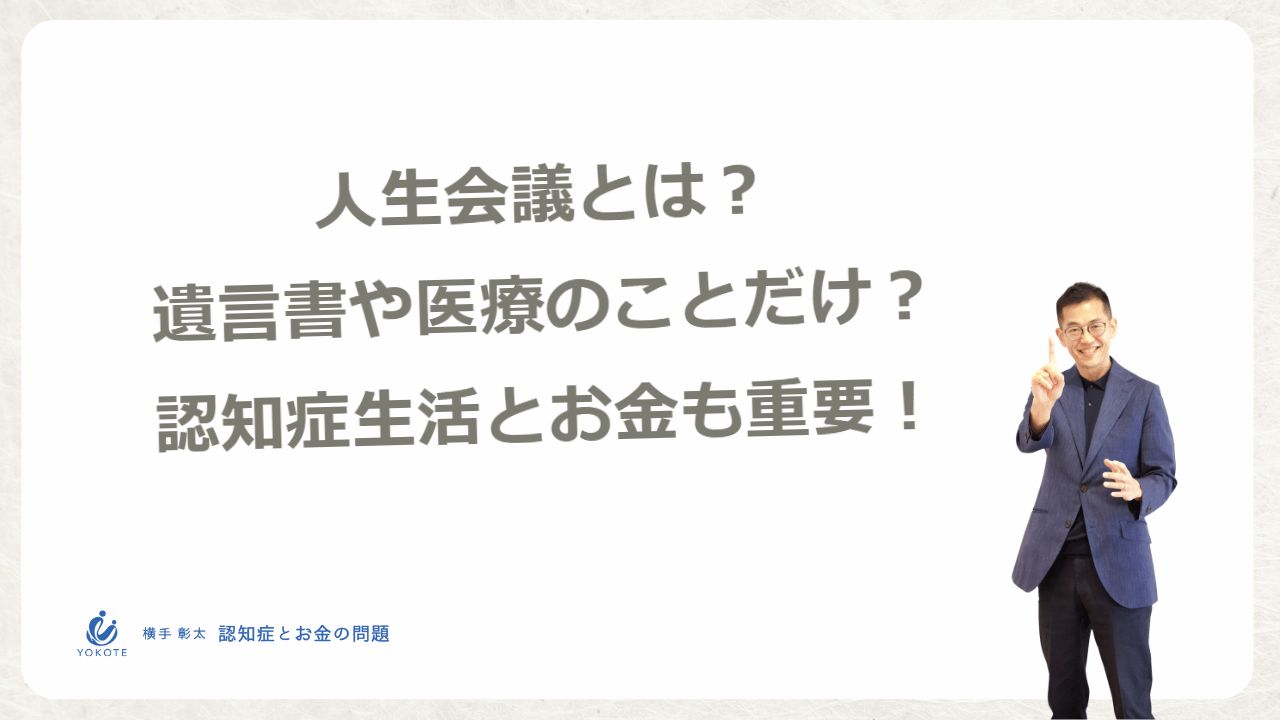
「人生会議」と聞くと、多くの人は延命治療や終末期医療について話し合う場をイメージします。
しかし、私、横手は家族信託コンサルタントとして現場に関わる中で、人生会議の本質はもっと手前にあると強く感じています。それは、認知症によって判断力を失う前に、自分の暮らしとお金をどう守るかを家族と共有し、現実的な備えを整えることです。
医療の希望だけでは、介護費用の支払い、不動産の管理、生活費の確保といった「生きている間の問題」は解決しません。
遺言書では支えられない部分をどう補うのか。家族信託や任意後見を含め、実務の視点から人生会議の本当の意味をわかりやすくお伝えしていきます。
この記事の筆者
認知症とお金の専門家・横手彰太。これまでに家族信託の締結サポートは累計350組以上、信託財産総額180億円超を担当してきました。
日本全国67ヶ所の公証役場での手続き実績があり、NHK「クローズアップ現代+」やAERA、プレジデント、日本経済新聞など多数メディアでも紹介されています。セミナー講師としても300回以上登壇し、一般のご家庭から税理士、不動産会社まで幅広い方々にお金と認知症対策について解説してきました。著書に『親が認知症になる前に知っておきたいお金の話』をはじめ計5冊があります。

親が認知症になると、財産管理や相続の問題が一気に複雑化します。
だからこそ、「備えるなら今」が大切です。親に認知症の症状がある場合はすぐに対策しないと後悔しますので無料相談をお申し込みください。家族信託を詳しく学びたい方は2時間以上の濃い内容で解説した特別YouTube動画もご案内していますので、ぜひ最後までご覧ください。
認知症とお金の問題は、本当に重要な問題です。
手遅れになる前に、しっかりと考えて行動しましょう。
「人生会議」とは何か――延命治療だけの話ではない
「人生会議」という言葉を聞いたことがある方は多いかもしれません。
これは厚生労働省が推進している「アドバンス・ケア・プランニング(ACP)」の日本語名称で、病気や老いによって自分の意思を伝えられなくなったときに備え、
「どのような医療・ケアを受けたいか」「どんな最期を迎えたいか」を前もって家族や医療関係者と話し合っておく取り組みです。
ただ、私、横手は現場で感じています。
多くの人が人生会議=延命治療をどうするかの話と捉えていますが、本当に大切なのは、もっと手前の「判断力を失う前の段階」での備えです。
つまり、「認知症になったとき、自分のお金や生活をどう守るか」という話こそ、実は人生会議の核心であると私は考えています。厚生労働省や人生会議の必要性を提唱している人たちは、医療的な側面、尊厳やQOLの観点からの人生会議のやり方を勧めていますが、現代において多くの人が認知症になる中で、急な事故や病態の急変で最期のときを考えることと同じように、認知機能が低下して自分で判断ができなくなった中でどのように生活していくのかリアルに考えて信頼できる人に託すことを考えなければなりません。
医療が進歩して、みんなが質の良い治療や療養を受けられる時代がだからこそ、認知機能が低下して自分でお金の管理や契約などの判断ができない状況になっても、何年も何十年もその状態で生活をしていかなくてはならない人がたくさんいます。
判断力を失うと「希望」だけでなく「手続き」も止まる
人生会議では、自分の希望を家族に伝えることが重視されます。
しかし、もし認知症が進行して判断能力を失ってしまうと、その「希望」をもとに行うはずの契約や手続きそのものができなくなるという現実があります。
たとえば、「延命治療は望まない」と決めていても、その治療を選択・拒否するための同意書に署名できなければ、家族が代筆することはできません。
「老人ホームに入りたい」と思っても、入居契約に本人の意思確認が必要です。
銀行口座から入居一時金を出そうとしても、判断能力が失われた時点で銀行口座が凍結されることもあります。
私、横手はこれを希望があっても動かせない現実と呼んでいます。
人生会議が医療や介護の話にとどまる限り、認知症によってお金や契約が止まる問題は解決できないのです。
「認知症になったら」では遅い、人生会議はお金の話から始める
私のもとに寄せられる相談の中で、最も多いのが「親が認知症になってからでは何もできない」という嘆きです。
家族は親の介護や生活費を支払いたくても、法的には代理権がなく、通帳を預かっていても銀行では「ご本人でなければ出金できません」と言われてしまう。
このような事態を防ぐには、「どんな介護を受けたいか」よりも先に、「誰が、どのようにその費用を管理・支払うか」を決めておく必要があります。日本では、大切な人に対して「お金のことは気にするな」というのが美徳のような価値観がありますが、認知症になった後、もしかすると何年何十年と症状が悪化していく中で生きていくことになりますので、その間の生活費や介護費用など、お金の問題を切り分けて考えていると子や孫の世代の生活を圧迫してしまうことも少なくありません。
人生会議とは、生き方だけでなく資金の流れを考える場でもあるべきです。
介護方針、医療の希望、そしてお金の管理――この三つは切り離せないテーマなのです。
遺言書では生きている間を守れない
多くの方は、「遺言書を書いておけば安心」と考えます。
しかし、遺言書の効力が発生するのはあくまで死後の話です。
本人が生きている間、つまり認知症が進行している時期の生活や医療費の支出、
不動産の管理などには遺言書は一切役に立ちません。
私、横手は現場で、「遺言書はあっても、介護費用を出せない」というご家族を何度も見てきました。
人生会議という言葉を聞いたときにこそ、「遺言」だけでなく、生きている間を守る仕組み――家族信託や任意後見契約――を一緒に考える必要があります。
家族信託は「生きている間の人生会議」を形にする
家族信託とは、本人(委託者)が元気なうちに、信頼できる家族(受託者)に財産管理を託す仕組みです。
この契約を交わしておけば、本人が認知症になっても、受託者が法律上の代理権を持って資金を管理し、介護費や医療費の支払い、不動産の売却、入居費の支出などを継続できます。
人生会議の場で「どんな生活を望むか」と同時に、「その生活を実現するためのお金を誰が管理するか」を話し合い、信託契約として具体化しておくことが、真に現実的な生き方の設計です。
私、横手はこの考え方を「実務としての人生会議」と呼んでいます。
それは、医療の希望だけではなく、経済的な持続可能性を伴った生き方の対話です。
人生会議は「亡くなる前」ではなく「判断できる今」行うもの
「人生会議」というと、「終末期の話だからまだ早い」と感じる方も少なくありません。
しかし、私、横手は断言します。
人生会議は亡くなる直前ではなく、判断できる今に行うものです。
人生会議は早く始めた方が良いというのは厚生労働省をはじめお偉いさんたちと同じような意見です。ただし、厚生労働省や研究機関などは、医療的な観点を中心に人生会議のやり方を組み立てるのに対し、私横手としては認知症などで誰かの助けを借りないと生活できない状況になった時にも、お金の面で親しい人たちに迷惑をかけない、誰にどのような助けを借りるかをあらかじめ決めておくということの重要性を強調しています。
認知症の進行によって判断力が失われると、贈与契約や家族信託契約など、法的な準備は一切できなくなります。
だからこそ、「まだ元気だからこそ話す」ことに意味があります。
どんな介護を受けたいか、どこで暮らしたいか、どのように財産を使いたいか――
人生会議で話し合うべきと言われている「延命するか」や「どこで死にたいか」などは、現実的なところ自分がどのように生きて死にたいかを考えることと同時に、生き続けることにかかるお金のことも考えなければなりません。
家族と共有し、単なる希望を伝えるだけではなく、家族との約束(契約)に落とし込むことが、現代の人生会議の本質だと私は考えています。
人生会議のゴールは「希望」と「資金」を両立させること
人生会議は、単に「どんな最期を迎えたいか」を話す場ではありません。
それは「どのように生きていくか」「そのためにお金をどう動かすか」を家族で共有するプロセスです。
私、横手はこれまで数多くの家族を支援する中で、こう感じています。
人生会議とは、命の話であると同時に、暮らしの継続の話でもある。
認知症という現実を見据えたうえで、お金・介護・想いを一体として整えること。
それこそが、真の意味での「人生をともに考える会議」なのです。