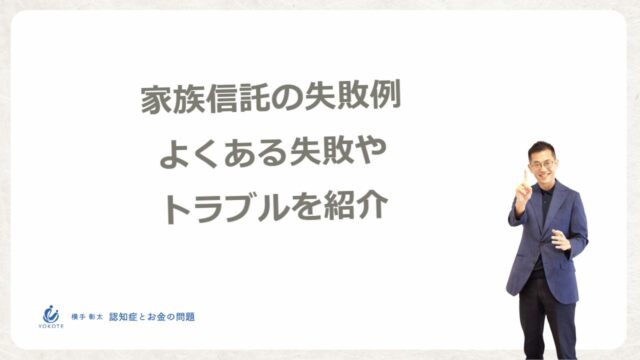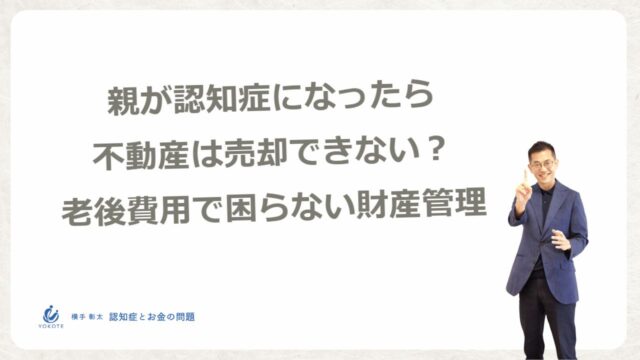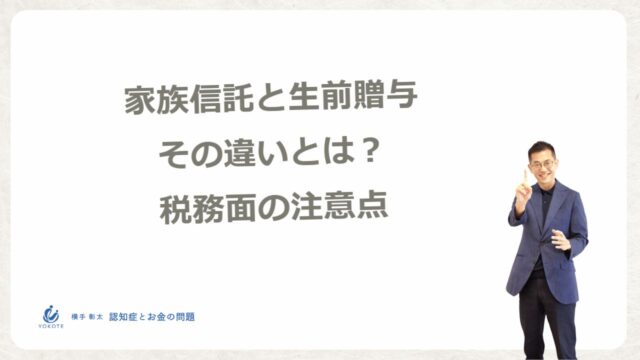家族信託とは?認知症対策に使える新しい財産管理
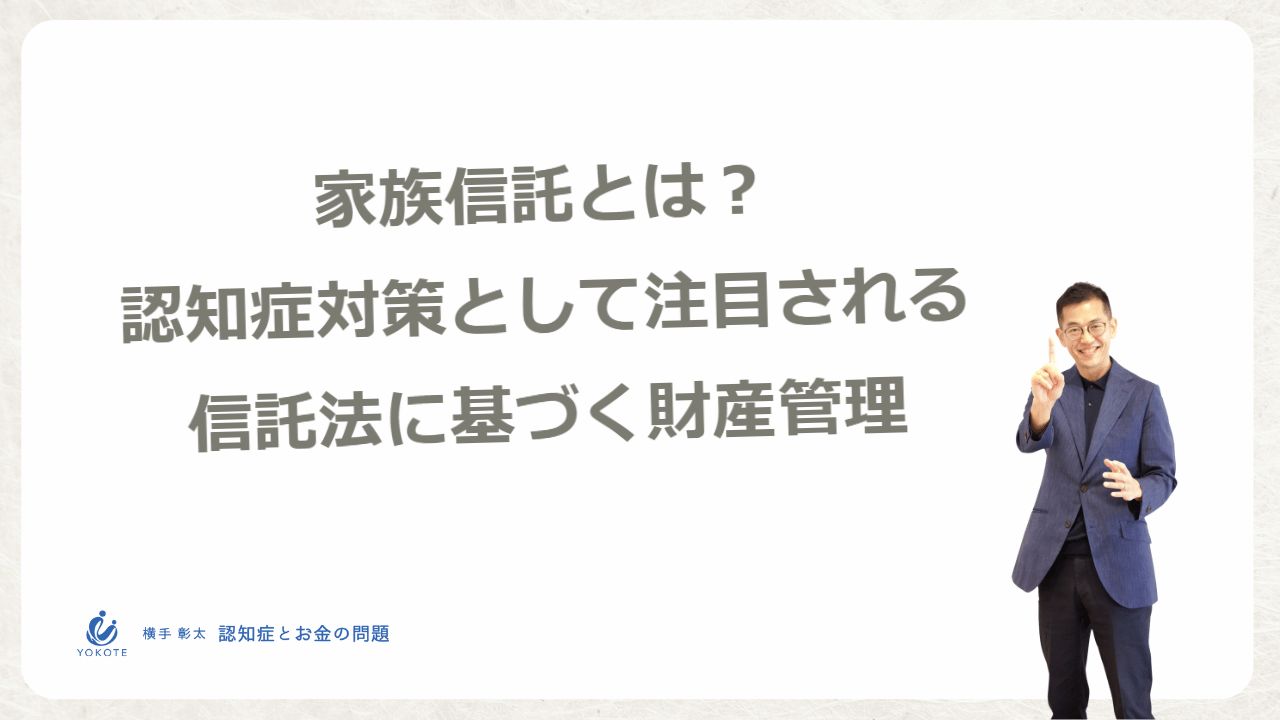
親が認知症になると、銀行口座の凍結や不動産の売却停止などによって、生活費や介護費用の確保が一気に難しくなることがあります。こうした「財産が眠ってしまうリスク」を回避するための新しい制度が「家族信託」です。
家族信託は、信頼できる家族に財産の管理や処分を託す仕組みで、認知症対策として注目されています。遺言や成年後見制度と比べても柔軟性が高く、資産の凍結を防ぎながら介護や相続をスムーズに進めることができます。
この記事では、家族信託の仕組みやメリット、デメリット、失敗事例を専門家の視点も交えて解説し、なぜ早めの対応が大切なのかを詳しく紹介します。
この記事の筆者
認知症とお金の専門家・横手彰太。これまでに家族信託の締結サポートは累計350組以上、信託財産総額180億円超を担当してきました。
日本全国67ヶ所の公証役場での手続き実績があり、NHK「クローズアップ現代+」やAERA、プレジデント、日本経済新聞など多数メディアでも紹介されています。セミナー講師としても300回以上登壇し、一般のご家庭から税理士、不動産会社まで幅広い方々にお金と認知症対策について解説してきました。著書に『親が認知症になる前に知っておきたいお金の話』をはじめ計5冊があります。

親が認知症になると、財産管理や相続の問題が一気に複雑化します。
だからこそ、「備えるなら今」が大切です。親に認知症の症状がある場合はすぐに対策しないと後悔しますので無料相談をお申し込みください。家族信託を詳しく学びたい方は2時間以上の濃い内容で解説した特別YouTube動画もご案内していますので、ぜひ最後までご覧ください。
認知症とお金の問題は、本当に重要な問題です。
手遅れになる前に、しっかりと考えて行動しましょう。
家族信託とは何か
家族信託とは、親が自分の財産の管理や処分を、信頼できる家族に託す仕組みです。
法律的には「信託法」に基づく制度で、財産を持つ人(委託者)が、財産を託される人(受託者)との間で契約を結びます。受託者は契約内容に従って財産を管理し、将来にわたって活用していきます。
たとえば親が自宅や土地を持っている場合、認知症で意思能力を失っても、受託者である子どもが売却や運用を行い、老人ホームの入居費や介護費用にあてることが可能になります。
老人ホームに入居しなくなる時までにゆっくり考えればいいやと思っている人も多いですが、老人ホームに入る時にはすでに認知症で日常生活が送れなくなっていたり判断能力がなくなっている状態のことが多いです。その状態から不動産を売却しようと思っても、本人に意思能力がない場合には契約が結べず、せっかくの財産が何もできない眠っている財産になってしまいます。ゆくゆくは相続するのだから家族が代わりに売却の手続きをすれば良い安易に考えていると、家族であっても本人抜きに売却などの契約を進めることができないという現実に直面します。このようなことを回避する方法が、事前に家族信託契約をしておき、財産を託された家族が契約内容に従って財産を管理するという「家族信託」の仕組みなのです。
横手彰太氏が語る「家族信託の本質」
家族信託コンサルタントの横手彰太氏は、家族信託を「財産のルール作り」「未来の設計図」と表現しています。遺言や成年後見制度と異なり、信託は生前から効力を持ち、相続発生後にもスムーズに財産を引き継ぐことができる点が最大の特徴です。横手氏によれば、家族信託を知っているかどうかで将来の安心感は大きく変わり、適切なタイミングで契約を結んでおくことが家族全員の生活を守る第一歩となります。
認知症と財産管理の問題
認知症になると、本人の意思能力が不十分と判断されるため、不動産の売却や銀行口座からの資金引き出しは不可能になります。実際には以下のような問題が生じます。
| 認知症発症後に起きる問題 | 具体的な影響 |
|---|---|
| 銀行口座の凍結 | 生活費や介護費用の支払いが困難になり、家族が立て替える必要が生じる |
| 不動産の売却不可 | 老人ホームの入居費を不動産売却でまかなう計画が崩れる |
| 資産の運用停止 | 投資や不動産賃貸の契約ができず、資産が「眠ったまま」になる |
| 家族間のトラブル | 財産管理や介護負担をめぐって兄弟姉妹間で対立が起こる可能性 |
成年後見制度を利用する方法もありますが、後見人には報酬が発生し、自由な資産運用は制限されます。
成年後見制度は「財産を守る仕組み」にはなりますが、家族信託のような「財産を活用する仕組み」にはなりにくいのです。
家族信託のメリットと可能性
家族信託を活用すれば、親が認知症を発症しても財産が凍結されず、必要なタイミングで資金を活用できます。信託契約の中で「財産をどのように使うか」を事前に取り決めておくことで、介護費用や生活費を安定的に確保できます。また、将来的な相続の際もスムーズに資産承継ができるため、きょうだい間のトラブルを防ぐ効果もあります。横手氏は、家族信託を「安心して介護や生活を続けられる未来への切符」と位置づけています。
家族信託のデメリット
家族信託は柔軟な制度ですが、万能ではありません。まず、契約の設計を誤ると「使いたいときに使えない」という不便さが生じる可能性があります。信託とは、信用して「委託」するというものなので、あらゆることを想定して委託する内容を組み入れた契約になっていないと、後々できないことや他の家族などから疑念を持たれたりすることがあります。
契約内容が不明確であれば受託者の判断に委ねざるを得ず、かえって家族間の不信感につながることもあります。
よく誤解されることなので、デメリットとしてお伝えしておくと、家族信託は遺留分や相続税の対象外になるわけではなく、相続に関する法的ルールが完全に排除できるものではありません。信託財産の管理には登記や税務申告などの手続きが伴い、費用や専門家のサポートが必要になる点もデメリットといえます。正しく理解せずに家族信託を始めることはかえってトラブルの種になります。
家族信託の失敗事例
実際の相談現場では、知識不足や準備不足による家族信託の失敗事例も見られます。
たとえば、軽度認知症の段階で「まだ契約できるだろう」と考えていたが、公証人の判断で意思能力が不十分とされ契約が成立しなかったケースがあります。また、家族の一部だけで契約を進めた結果、他のきょうだいが「自分に不利だ」と感じてトラブルに発展することもあります。
さらに、専門家に相談せず自分たちだけで契約書を作成したため、内容が不完全で実際に資産を動かすときに使えなかったという事例もあります。これらはすべて、早めに専門家に相談していれば防げた問題です。失敗を避けるためには、家族全体で話し合い、将来の目的を共有し、専門的な知識を持つサポートを受けながら契約を設計することが不可欠です。
専門家のサポートが必要な理由
家族信託は自由度が高い制度である一方、契約内容や設計を誤ると「使いたいときに使えない」「税務上不利になる」などの問題が起こる可能性があります。そのため、専門家の知見を取り入れた契約設計が重要です。横手氏のように実務経験が豊富な専門家と相談することで、本人にとっても家族にとっても最適な形で信託を進めることができます。
早めの対応が重要
認知症の症状が出てしまうと、家族信託契約は締結できなくなります。軽度認知症の段階であっても、公証人や医師の判断によっては契約が難しい場合があります。そのため「まだ元気だから大丈夫」と先送りせず、早めに備えることが何よりも大切です。
まとめ
家族信託は、認知症対策として新しい財産管理の選択肢を提供してくれる制度です。正しい知識と専門家のサポートを得ることで、家族の将来を守り、安心した生活を続けることができます。
もし親が軽度認知症の可能性がある、あるいは将来に不安を感じている場合は、今すぐ行動に移すことが必要です。対応が遅れると選択肢は限られてしまいます。ぜひ早めに家族信託について学び、まずは無料相談をお申し込みください。