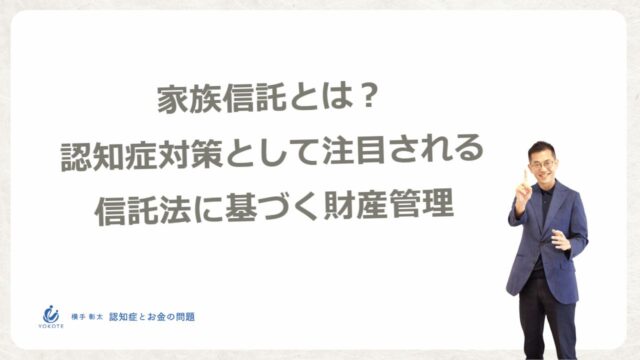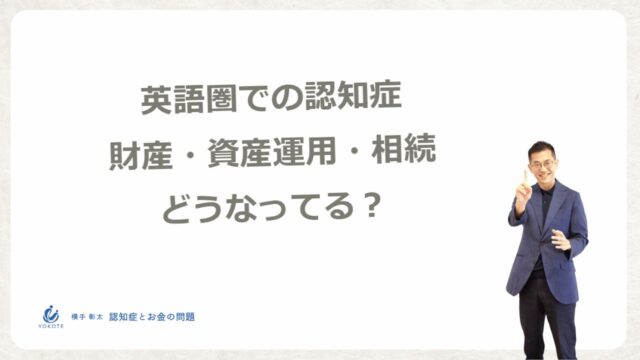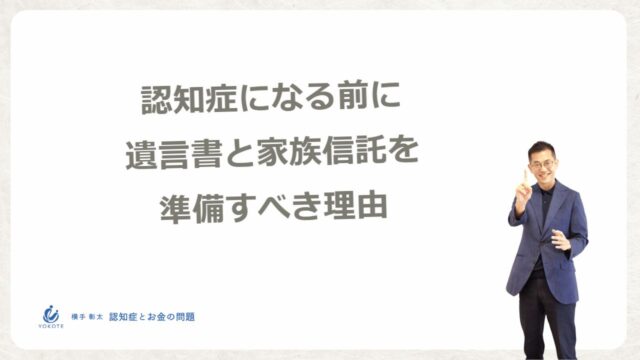公証役場とは?遺言・任意後見・家族信託を公正証書にする理由
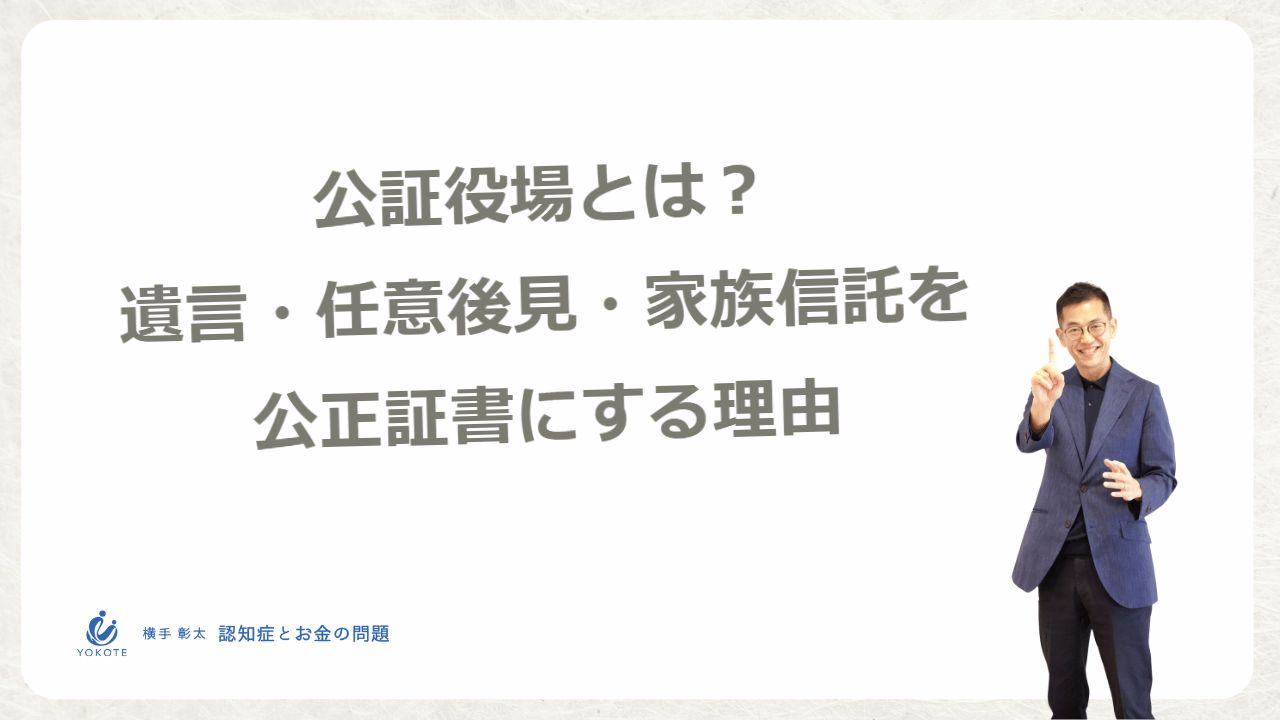
「親が認知症になったら、銀行口座からお金が下ろせなくなった」「遺言書を書いていたのに無効と言われた」――私、横手はこれまで数多くの家庭で、そんなトラブルの相談を受けてきました。多くの方に共通していたのは、「公証役場での手続きを知らなかった」という点です。
公証役場は、法務省のもとで「公証人」が法律行為を公的に証明する場所です。遺言書、任意後見契約、家族信託などを「公正証書」という形にしておけば、認知症や相続をめぐる争いを未然に防ぐことができます。
この記事では、家族信託コンサルタントである私・横手彰太が、公証役場とはどのような場所なのか、公正証書でできること、そしてなぜ認知症とお金の問題に深く関わるのかを、わかりやすく解説していきます。
この記事の筆者
認知症とお金の専門家・横手彰太。これまでに家族信託の締結サポートは累計350組以上、信託財産総額180億円超を担当してきました。
日本全国67ヶ所の公証役場での手続き実績があり、NHK「クローズアップ現代+」やAERA、プレジデント、日本経済新聞など多数メディアでも紹介されています。セミナー講師としても300回以上登壇し、一般のご家庭から税理士、不動産会社まで幅広い方々にお金と認知症対策について解説してきました。著書に『親が認知症になる前に知っておきたいお金の話』をはじめ計5冊があります。

親が認知症になると、財産管理や相続の問題が一気に複雑化します。
だからこそ、「備えるなら今」が大切です。親に認知症の症状がある場合はすぐに対策しないと後悔しますので無料相談をお申し込みください。家族信託を詳しく学びたい方は2時間以上の濃い内容で解説した特別YouTube動画もご案内していますので、ぜひ最後までご覧ください。
認知症とお金の問題は、本当に重要な問題です。
手遅れになる前に、しっかりと考えて行動しましょう。
公証役場の役割と公証人の立場
公証役場(こうしょうやくば)とは、国の法務局の監督下で「公証人」が法律行為を公的に証明するための文書を作成する場所です。
公証人は、裁判官や検察官など法律実務の経験を積んだ法律家が法務大臣に任命されており、私たちの暮らしの中でトラブルを未然に防ぐ「予防法務」を担っています。つまり、公証役場は裁判が起こる前に、法的な証明力のある文書を作っておくための場所なのです。
公証人は、公証人法(昭和24年法律第53号)に基づいて任命される「法務大臣の任命職」です。
公証人法第13条には、次のように定められています。
(公証人の資格)
第13条 公証人は、次に掲げる者のうちから法務大臣が任命する。
一 裁判官、検察官又は弁護士の職に10年以上あった者
二 大学で法学の教授又は准教授の職にあった者
三 法務事務官の職にあった者その他法務に関し学識経験のある者で法務大臣が適当と認めた者
つまり、一般の人が試験を受けてすぐになれる職ではなく、法務の実務経験を長く積んだ専門家が法務大臣の選考を経て任命される仕組みになっています。
多くの公証人は、退官した裁判官・検察官・弁護士などが任命されます。
私、横手はこれまで多くのご家族から「親が認知症になったら銀行でお金が下ろせない」「遺言書を書いていたけれど、自筆だから効力に不安がある」といった相談を受けてきました。こうしたトラブルの多くは、公証役場で公正証書を作っておけば防げたケースが少なくありません。
公正証書とは何か
「公正証書」とは、公証人が本人の意思を確認し、法律に基づいた手続きのもとで作成する公文書のことです。
民法第969条以下には遺言公正証書に関する規定があり、公証人が本人の意思を確認しながら作成・署名・押印を行うことが明記されています。公正証書は、後から「書いた・書いていない」「署名が違う」などと争われにくく、裁判でも高い証拠力を持ちます。
さらに、公正証書には執行力が認められるものもあります。たとえば金銭の貸し借りや家賃契約などに関する公正証書では、「支払わなければ強制執行できる」という条項を入れることができるため、訴訟を経ずに差押えが可能になる場合があります。
公正証書でできること
公正証書は、遺言、任意後見契約、金銭消費貸借契約、離婚給付契約、会社の定款など、さまざまな法律行為に使われます。しかし、私、横手が特に重要だと感じているのは「認知症とお金の問題」に関わる分野です。
中でも代表的なのが「公正証書遺言」と「任意後見契約」です。
公正証書遺言は、本人の意思を公証人が確認したうえで作成するため、形式不備で無効になるリスクがなく、遺言者が亡くなった後の相続トラブルを大きく減らせます。また、認知症が進行すると自筆証書遺言は書けなくなるため、判断能力が十分なうちに公正証書遺言を作成しておくことが極めて重要です。
任意後見契約は、将来認知症などで判断能力が低下したときに備えて、あらかじめ信頼できる人に財産管理や契約手続きを任せておく仕組みです。この契約も公正証書で作成する必要があります。私が多くの現場で見てきたように、親の通帳が凍結されて生活費が出せない、介護施設の契約が進まないといった事態は、任意後見契約をきちんと結んでおけば避けられることが多いのです。
一方で、会社設立時の定款認証なども公証役場の仕事ですが、これは法人の登記のための形式的なものです。家族の生活や財産を守るという観点では、やはり遺言や任意後見契約が中心となります。
家族信託との関係
ここで多くの方が気になるのが「家族信託と公証役場の関係」です。家族信託契約そのものは、必ずしも公正証書で作成しなければならないわけではありません。
しかし、私、横手は実務の立場から、信託契約を公正証書にしておくことを強く推奨しています。理由は二つあります。
第一に、将来、親が認知症になったあとに「この契約は本当に本人の意思だったのか」と疑われることを防ぐためです。
第二に、銀行や不動産登記などの手続きで、公正証書であることが信用力を高めるからです。
つまり、公証役場で信託契約書を作成しておけば、親の老後の資産管理をより安心・確実に進めることができるのです。
公証役場での手続きの流れと費用
実際に公証役場で公正証書を作る際は、本人確認資料(運転免許証やマイナンバーカードなど)を提示し、公証人が面談で意思を確認します。遺言の場合は証人二人の立ち会いが必要で、任意後見契約の場合は本人と受任者双方が公証人の前で説明を受け、署名します。
費用は内容や財産の額によって変動しますが、例えば任意後見契約で1〜2万円程度、遺言公正証書では3〜5万円前後が一般的です。大きな遺産や複雑な内容の場合は、報酬規程に基づき加算されます。公証人手数料令により全国一律の料金体系が定められているため、どの公証役場でも大きな差はありません。
認知症とお金のトラブルを防ぐために
私は現場で、親の認知症が進んでから慌てて相談に来られるご家族を何度も見てきました。そのときにはもう、公正証書を作ることはできません。判断能力が失われてしまうと、本人の意思確認ができず、公証人も作成を引き受けられないのです。
だからこそ、元気なうちに「自分の財産をどう守るか」「誰に任せるか」を公正証書で形にしておくことが何よりも大切です。家族信託や任意後見、公正証書遺言などは、単なる法律書類ではなく、「家族の未来を守る準備」です。
私、横手はこれまで多くのご家庭でその重要性を実感してきました。もし、あなたの家族にも「万が一のとき困らないようにしておきたい」と思う方がいれば、まずは公証役場で何ができるのかを知ることから始めてください。それが、後悔しない老後と安心できる家族の生活につながる第一歩です。