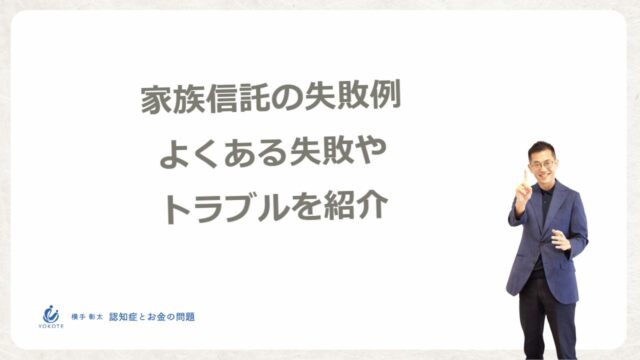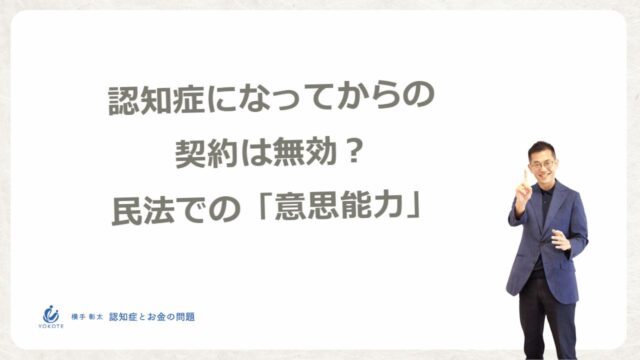認知症で意思能力に関する判例、契約の有効性のライン
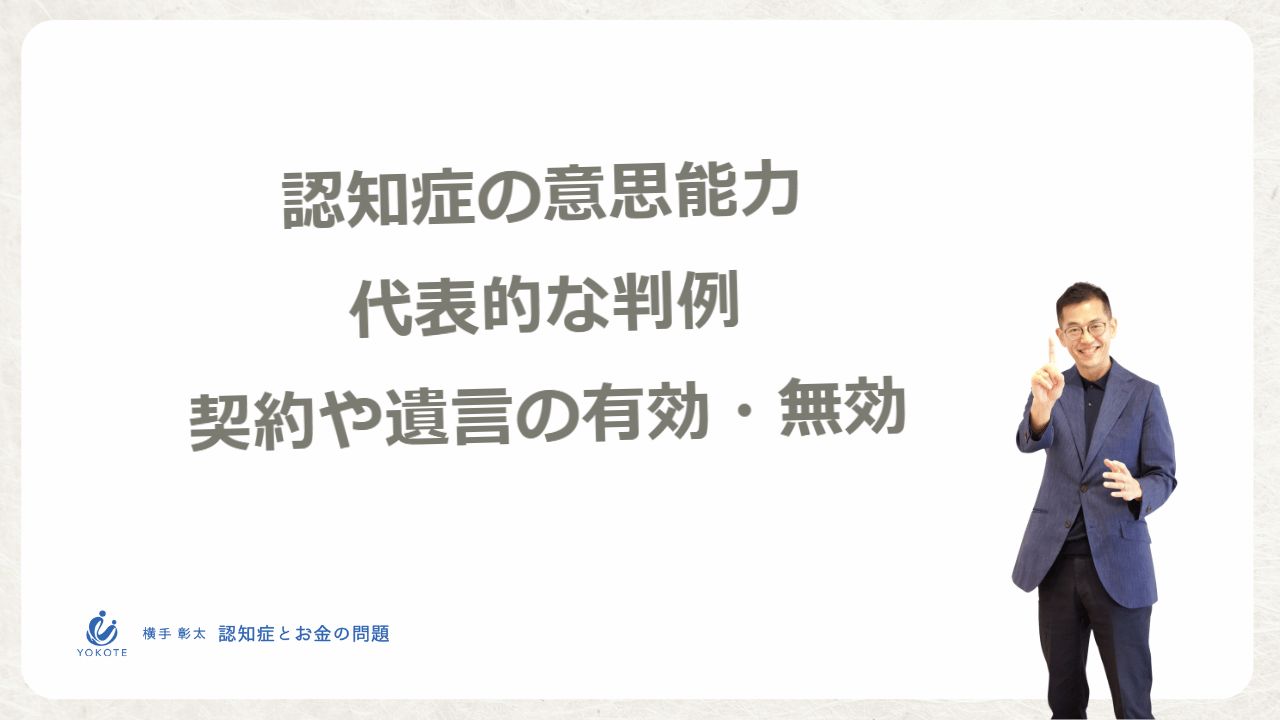
認知症の進行により、本人が行った契約が「有効か無効か」をめぐって争われるケースは少なくありません。民法では「意思能力」を欠いた状態で行った契約は無効とされていますが、その判断は一律ではなく、裁判例によって具体的な基準が示されています。売買契約や贈与契約、遺言など、さまざまな事例の中で、どの程度の判断力があれば契約が有効と認められるのか、あるいは無効とされるのかが議論されてきました。この記事では、代表的な判例をもとに、契約の有効性のラインを分かりやすく整理し、家族信託をはじめとする財産管理契約を検討する際に押さえておきたいポイントを解説します。
この記事の筆者
認知症とお金の専門家・横手彰太。これまでに家族信託の締結サポートは累計350組以上、信託財産総額180億円超を担当してきました。
日本全国67ヶ所の公証役場での手続き実績があり、NHK「クローズアップ現代+」やAERA、プレジデント、日本経済新聞など多数メディアでも紹介されています。セミナー講師としても300回以上登壇し、一般のご家庭から税理士、不動産会社まで幅広い方々にお金と認知症対策について解説してきました。著書に『親が認知症になる前に知っておきたいお金の話』をはじめ計5冊があります。

親が認知症になると、財産管理や相続の問題が一気に複雑化します。
だからこそ、「備えるなら今」が大切です。親に認知症の症状がある場合はすぐに対策しないと後悔しますので無料相談をお申し込みください。家族信託を詳しく学びたい方は2時間以上の濃い内容で解説した特別YouTube動画もご案内していますので、ぜひ最後までご覧ください。
認知症とお金の問題は、本当に重要な問題です。
手遅れになる前に、しっかりと考えて行動しましょう。
認知症と契約有効性の関係
認知症を患った方が結んだ契約について、「有効か無効か」が争われる事例は少なくありません。
民法第3条の2には以下の規定があります。
民法 第二章 第3条の2(意思能力)
法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は、無効とする。
民法第3条の2では、意思能力を欠く場合の法律行為は無効と定められていますが、実際にその判断がどう下されるのかは、裁判例によって具体化されてきました。特に、売買契約や贈与契約、遺言などでは、当時の認知症の程度や行為の内容が詳しく検討され、判決が出ています。
判例に見る認知症の人の意思能力のライン
意思能力の有無は、医学的な診断だけでは決まりません。契約の内容を理解し、自らの行為がもたらす結果を認識できていたかどうかが基準となります。
例えば、ある判例では認知症が進行していた高齢者が土地の売買契約を結んだものの、本人が契約内容を十分に理解していなかったとして無効とされました。
一方、別の事例では、医師により軽度認知症と診断されていたものの、契約時に内容を説明されて理解していたと認められ、有効と判断されたケースもあります。つまり、単に「認知症」という診断名があるだけでは無効とはならず、契約行為の時点における具体的な判断能力が重視されるのです。
認知症による意思能力が争点となった代表的な判例一覧表
| 裁判年月日 | 事件の概要 | 裁判所の結論 |
|---|---|---|
| 東京地裁平成16年2月12日判決 | 高齢者が認知症の症状を抱えた状態で不動産売買契約を締結。契約当時、内容を理解できていなかったと相続人が主張。 | 本人に契約内容を理解する能力が欠けていたとして、売買契約は無効と判断。 |
| 東京高裁平成19年6月28日判決 | 軽度認知症の診断を受けた高齢者が贈与契約を行ったが、契約時に意思確認が行われていた。 | 契約時点で一定の理解があったと認められ、贈与契約は有効と判断。 |
| 大阪地裁平成24年3月22日判決 | 認知症が進行した高齢者が預金を引き出し、多額の贈与を実行。後に親族間で有効性が争われた。 | 本人に意思能力が欠如していたと認められ、贈与契約は無効と判断。 |
| 東京地裁平成29年7月6日判決 | 高齢者が施設入居前に遺言を作成。軽度認知症と診断されていたが、公証人の立ち会いのもと作成された。 | 公証人の確認で意思能力が認められ、遺言は有効と判断。 |
家族信託契約における意思能力の重要性
裁判例からも分かるように、認知症の進行度や状況に応じて「契約が有効か無効か」が判断される際の基準は、本人が契約内容を理解し意思決定できるかどうか、つまり「意思能力」にあります。家族信託は裁判所での裁判で一部行われるものもありますが、多くのケースでは公証役場の公証人や金融機関の担当者、司法書士の方などが意思能力を確認していくことになります。売買契約や贈与契約だけでなく、家族信託の契約においても同じように問われます。
家族信託の契約は単純な売買や贈与とは異なり、より複雑な内容を含みます。
例えば、不動産を信託財産とする場合、その不動産の権利関係や処分の方法、将来的に誰にどのように財産を渡すのかなど、契約書に具体的かつ個別の事項を詳細に定めていきます。さらに、預金や有価証券など複数の財産を含める場合には、それぞれの取り扱いや受益権の分配についても明確に記載する必要があります。
したがって、家族信託契約を有効に結ぶためには、本人が「この財産を信託する意味は何か」「家族に託す内容はどういうことなのか」を理解し、合理的に判断できる状態であることが不可欠です。判例が示すように、意思能力の有無は後に争いとなる場合があるため、契約締結時に専門家が関与し、本人の理解度を丁寧に確認して記録に残すことが極めて重要です。
この点からも、家族信託は認知症が進行してからでは遅く、軽度の段階であっても十分な意思確認ができるうちに進めることが望ましいといえます。
家族信託における実務上の注意点
家族信託契約は、銀行口座や不動産の管理・承継など大きな法的効果を伴うため、契約締結時の意思能力が厳しく問われます。公証人は契約の場で本人に内容を説明し、理解できているかを確認します。もし合理的に説明ができなければ、契約は成立しません。実務では「軽度認知症の段階でギリギリ契約ができたが、その後すぐに進行してしまった」というケースもありますが、それでも有効性は「契約時の能力」が基準となります。
判例から見える教訓
これらの判例から導かれる教訓は明確です。意思能力の有無は契約時点で判断され、契約後に「認知症だったのでは」と疑義が出ると裁判で無効と争われる可能性があります。特に遺言や不動産の売買、家族信託といった大きな契約は、後に家族間でトラブルに発展するリスクが高いため、確実な証拠と公的な手続きを整えておく必要があります。
早めの準備が家族を守る
私はこれまで多くの家族信託を支援してきましたが、「もう少し早く動いていれば」というご相談を何度も受けました。認知症の症状が出てからでは、意思能力の欠如によって契約が認められないリスクが一気に高まります。民法や判例の解釈を踏まえれば、家族信託は意思能力が十分に保たれている段階で契約することが不可欠です。
まとめ
認知症で意思能力を問われた判例は、契約の有効性がどこで線引きされるのかを私たちに示しています。契約は「できるときにやっておく」ことが何よりの安心につながります。もし親に軽度の認知症の兆候が見られる場合、今のうちに家族信託を含めた対策を検討するべきです。少しでも不安を感じている方は、ぜひ早めに無料相談をお申し込みください。専門家の知見を活かし、本人と家族にとって最良の形を一緒に設計していきましょう。