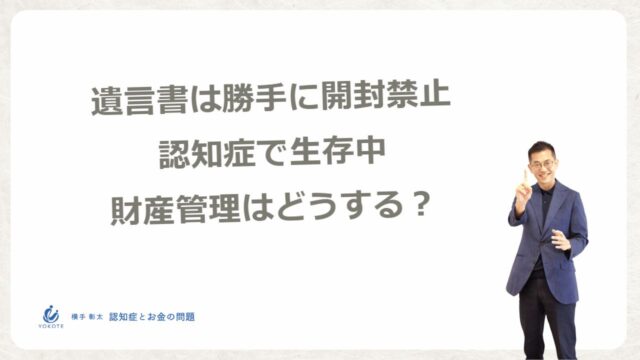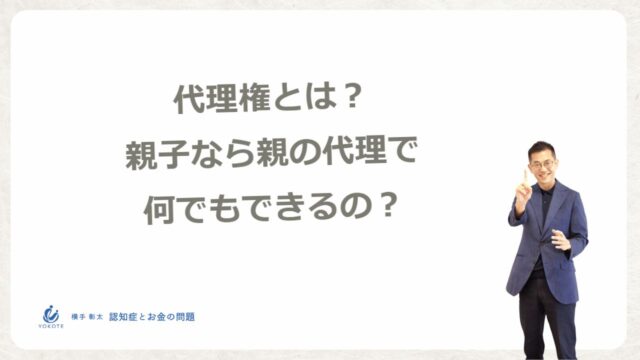認知症の親の介護費用を親の口座から引き出すのは法的に問題ない?
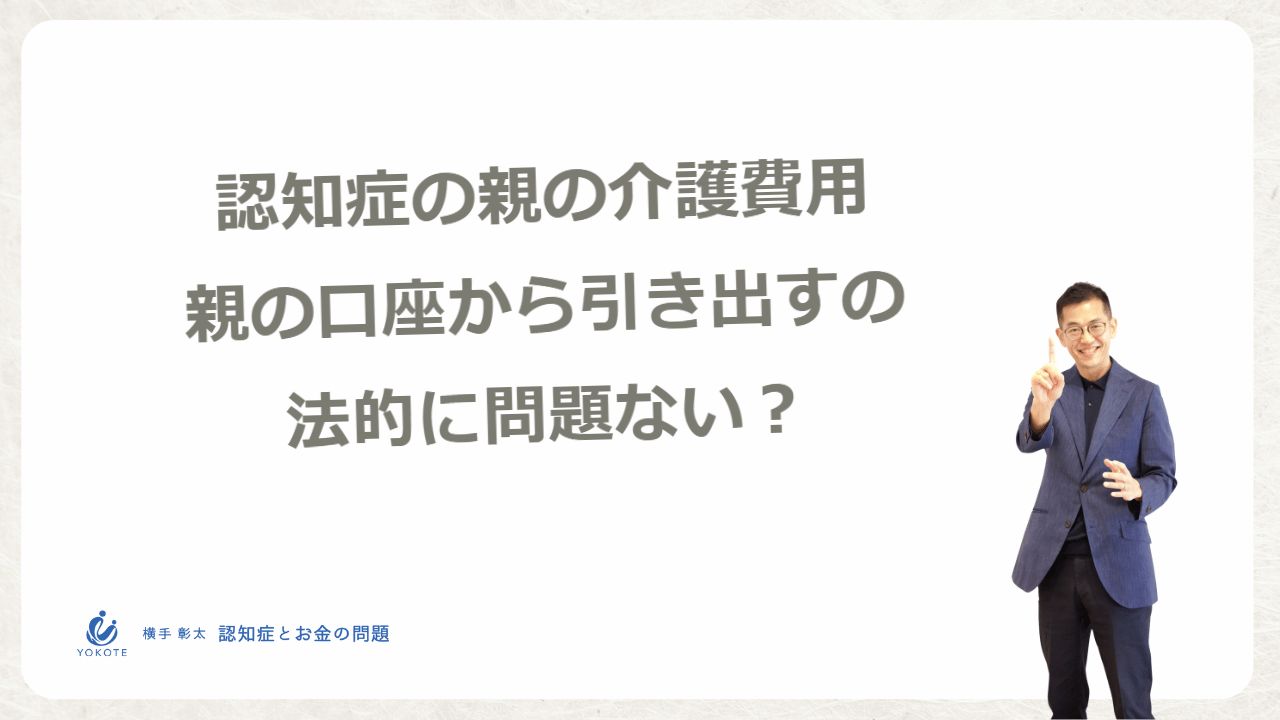
「母の介護費を払うために、母の口座からお金を引き出しているけれど、これって問題ないの?」
私、横手はこれまで多くのご家庭から、そんなご相談を受けてきました。
認知症の親を支えるために家族が代わりに支払いを行う――その気持ちは純粋な「親のため」です。
しかし、法的には本人の同意が確認できない状態で家族が口座を動かすことは、原則として認められていません。
銀行の立場から見れば、たとえ家族であっても「第三者」による出金とみなされ、口座が凍結される可能性もあります。
この記事では、家族信託コンサルタントの私・横手彰太が、認知症の親の口座をめぐる法律上の問題点、そして介護費を「正しく」「安心して」支払うための備え方について、実務経験に基づいて詳しく解説します。
この記事の筆者
認知症とお金の専門家・横手彰太。これまでに家族信託の締結サポートは累計350組以上、信託財産総額180億円超を担当してきました。
日本全国67ヶ所の公証役場での手続き実績があり、NHK「クローズアップ現代+」やAERA、プレジデント、日本経済新聞など多数メディアでも紹介されています。セミナー講師としても300回以上登壇し、一般のご家庭から税理士、不動産会社まで幅広い方々にお金と認知症対策について解説してきました。著書に『親が認知症になる前に知っておきたいお金の話』をはじめ計5冊があります。

親が認知症になると、財産管理や相続の問題が一気に複雑化します。
だからこそ、「備えるなら今」が大切です。親に認知症の症状がある場合はすぐに対策しないと後悔しますので無料相談をお申し込みください。家族信託を詳しく学びたい方は2時間以上の濃い内容で解説した特別YouTube動画もご案内していますので、ぜひ最後までご覧ください。
認知症とお金の問題は、本当に重要な問題です。
手遅れになる前に、しっかりと考えて行動しましょう。
「親のためだから」でも通用しない法律の壁
私、横手はこれまでに数多くのご家族から、「親の介護費を親の口座から引き出しているけれど、これって大丈夫なんですか?」という相談を受けてきました。
多くの場合、家族が悪意を持ってお金を使っているわけではなく、親の生活費や介護費、病院代などをきちんと支払うために動いているのです。
しかし、法的な観点から言えば、「親の口座から家族が勝手に引き出す行為」は、たとえ親のためであっても原則として違法行為(財産管理権の侵害)に該当する可能性があります。
銀行は「本人の意思確認ができない状態では、本人以外が口座を動かすことは認めない」という立場を取っています。
つまり、「親のために」「正しく使っている」という理由では法的な正当性は担保されないのです。
この認識のずれこそ、私が現場で一番多く目にする“トラブルの芽”です。
銀行は、家族でも代理権がなければ出金できない
金融機関は「本人確認義務」が非常に厳格です。
銀行法や犯罪収益移転防止法に基づき、預金者本人の意思が確認できない状況下では、家族であっても口座を動かすことができません。
たとえば、次のような状況を考えてみましょう。
| 状況 | 銀行の対応 | 備考 |
|---|---|---|
| 親が病気や認知症で窓口に行けない | 原則、出金不可 | 委任状があっても判断能力がなければ無効 |
| 家族が代理でATMやネットバンキングを使用 | 利用規約違反の可能性 | ID・暗証番号の使用を他人に委ねるのは違法行為 |
| 成年後見人・任意後見人・受託者がいる | 出金可 | 正式な代理権に基づく場合のみ可能 |
実際に、銀行員が「お母さまはご自身で意思を確認できますか?」と尋ね、少しでも不安がある場合には口座を凍結することがあります。
これは、家族を疑っているわけではなく、金融機関としてのリスク管理の一環なのです。
「黙って引き出す」は、あとで家族間トラブルの火種に
私、横手が実務で感じるもう一つの大きな問題は、家族間での誤解や不信です。
兄弟のうち一人が親の通帳やキャッシュカードを管理していると、「お金を勝手に使っているのではないか」と疑われるケースが少なくありません。
たとえ全額を介護費用や病院代に使っていたとしても、領収書が残っていなければ他の相続人に説明できず、後々「遺産の使い込み」として揉めることもあります。
特に、親が亡くなった後の相続の場面では、「あの時いくら引き出したのか」「何に使ったのか」が問題になり、結果として家族の関係が壊れてしまうケースもあります。
つまり、法律上も感情面でも、曖昧な管理は家族を守れないのです。
認知症の財産管理に「法的な代理権」を持たせる方法
では、家族が安心して親の財産を管理するにはどうすればいいのでしょうか。
私、横手は現場で「二つの仕組み」を中心に提案しています。
ひとつは家族信託、もうひとつは任意後見契約です。
家族信託は、親(委託者)が判断能力のあるうちに、信頼できる家族(受託者)に財産を託しておく契約です。
信託契約を結んでおけば、親が認知症になっても、受託者が信託口口座を通じて生活費や介護費を支払うことができます。
この仕組みの利点は、裁判所の監督を受けずに家族の中で柔軟な財産管理ができる点にあります。
一方の任意後見契約は、親が将来、判断能力を失ったときに備えて、あらかじめ信頼できる人に財産管理や生活支援を委ねる制度です。
ただし、任意後見契約は、家庭裁判所に任意後見監督人が選任されて初めて効力を持ちます。
そのため、「すぐに使える制度」ではなく、将来型の仕組みだと理解しておく必要があります。
| 比較項目 | 家族信託 | 任意後見契約 |
|---|---|---|
| 主な目的 | 財産の管理・運用・承継 | 生活・医療・介護の支援 |
| 契約の有効時期 | 契約直後から有効 | 判断能力低下後に発効 |
| 裁判所の関与 | 不要 | 必要(監督人がつく) |
| 柔軟性 | 高い(家族間で運用可) | 制限あり(法的監督下) |
私、横手は実務上、この二つを「補完し合う制度」として併用することを勧めています。
家族信託でお金を守り、任意後見契約で生活を支える――それが最も現実的で安心な形です。
「親のために」は、法的にも備えてこそ意味がある
家族の誰もが「親のために」と思って動いているはずです。
しかし、法律の世界では「善意」だけでは通用しません。
意思確認ができない親の財産を動かすには、法的根拠のある代理権限が不可欠です。
私、横手は現場で何度も「親のお金を守るつもりが、結果的にトラブルになってしまった」家族を見てきました。
通帳を預かる、キャッシュカードを使う ―― その一つひとつに法的リスクが伴います。
だからこそ、信託や後見といった制度を「親が元気なうちに」整えておくことが、家族を守る最大の思いやりなのです。
口座を守ることが、家族を守ること
認知症の親の介護費用を親の口座から引き出す行為は、たとえ家族であっても法的には認められません。
無理に出金を続ければ、口座凍結や親族間トラブル、さらには法的責任に発展するおそれもあります。
大切なのは、「どうやって親のお金を正しく使える状態にしておくか」。
その答えが、家族信託や任意後見契約といった事前の備えにあります。
私、横手はいつもお伝えしています。
「親のために」お金を動かすなら、法律に守られた方法で――。
それこそが、真に親孝行な行動なのです。