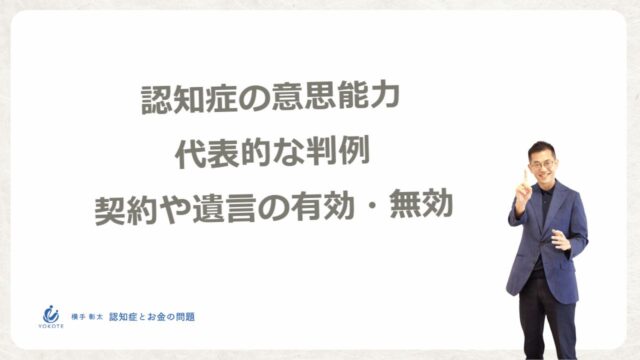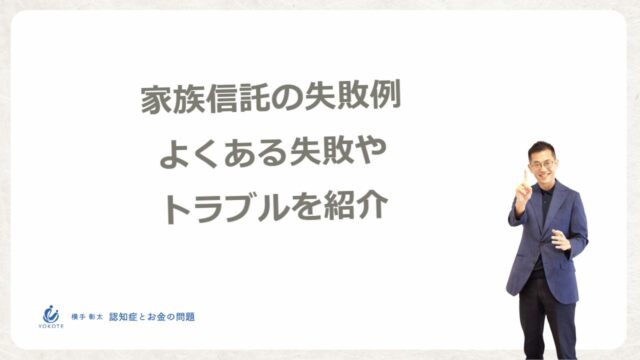認知症になってからの契約は無効?民法での解釈
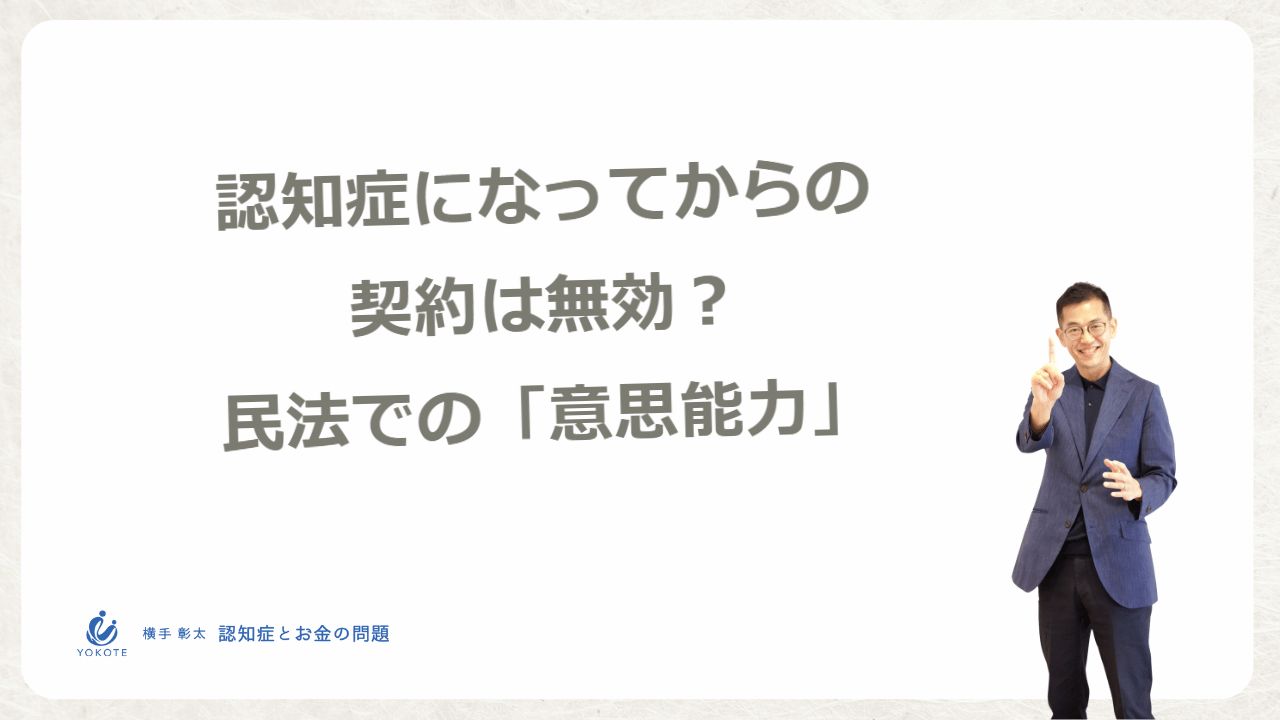
親が認知症になった後に、家族信託や財産管理の契約を結ぶことはできるのか――これは多くのご家族が直面する切実な問題です。民法では契約には「意思能力」が必要とされ、認知症によって判断力が失われると契約自体が無効となる可能性があります。実際、公証人は契約の場面で本人の理解力を確認し、十分な意思能力がなければ契約を成立させません。
この記事では、民法における意思能力の規定とその解釈、認知症と契約の有効性の関係を解説し、なぜ早めに家族信託などの対策を取ることが重要なのかを専門家の視点でわかりやすくお伝えします。
この記事の筆者
認知症とお金の専門家・横手彰太。これまでに家族信託の締結サポートは累計350組以上、信託財産総額180億円超を担当してきました。
日本全国67ヶ所の公証役場での手続き実績があり、NHK「クローズアップ現代+」やAERA、プレジデント、日本経済新聞など多数メディアでも紹介されています。セミナー講師としても300回以上登壇し、一般のご家庭から税理士、不動産会社まで幅広い方々にお金と認知症対策について解説してきました。著書に『親が認知症になる前に知っておきたいお金の話』をはじめ計5冊があります。

親が認知症になると、財産管理や相続の問題が一気に複雑化します。
だからこそ、「備えるなら今」が大切です。親に認知症の症状がある場合はすぐに対策しないと後悔しますので無料相談をお申し込みください。家族信託を詳しく学びたい方は2時間以上の濃い内容で解説した特別YouTube動画もご案内していますので、ぜひ最後までご覧ください。
認知症とお金の問題は、本当に重要な問題です。
手遅れになる前に、しっかりと考えて行動しましょう。
民法における「意思能力」と契約の有効性
民法では、契約を結ぶ際には「意思能力」が必要とされています。
意思能力とは、契約の意味や内容を理解し、合理的に判断できる能力を指します。つまり、本人が自らの行為によってどのような結果が生じるのかを理解できない状態で結ばれた契約は、無効とされる可能性が高いのです。認知症が進行し、意思判断が不十分と見なされれば、たとえ家族信託契約を結んでも効力を持たないことになります。
関連する法律条文
民法第3条の2には以下の規定があります。
民法 第二章 第3条の2(意思能力)
法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は、無効とする。
この条文は、契約や遺言など、法律上の効果を生じさせる行為を有効に行うためには、本人に「意思能力」が必要であることを明記しています。
民法第3条の2(意思能力)の条文の解釈
ここでいう意思能力とは、自分の行為がどのような法律効果をもたらすかを理解し、合理的に判断できる能力を指します。例えば、売買契約であれば「お金を払えば商品が手に入る」「商品を渡せば代金を受け取れる」といった因果関係を理解できるかどうかが基準となります。
認知症の進行によって判断力が低下し、契約の意味や結果を理解できなくなると「意思能力を欠く」とされ、その契約は無効になります。特に家族信託契約のように複雑で長期的な効果を伴う法律行為では、より高いレベルの理解力が求められるため、軽度認知症の段階でも契約が認められないことがあり得ます。
契約無効の判断は誰が行うのか実務における判断
実務上、契約の有効性は公証人や裁判所が「本人に意思能力があるかどうか」を判断します。契約締結の場面では、本人が契約内容を説明されて理解できているか、質問に対して合理的に答えられるかなどが確認されます。したがって「医師の診断書でまだ軽度」とされていても、実際には契約が無効とされる可能性があるのです。
公証人による事前の確認
家族信託契約を公正証書で作成する場合、公証人が本人の意思能力をその場で確認します。契約内容の説明を受けて理解できているか、質問に対して合理的に答えられるかなどが基準になります。もし理解が不十分と判断されれば、その時点で「契約は作成できない」=無効扱いとなります。
金融機関や不動産登記官の対応
信託契約に基づいて銀行口座を開設したり、不動産の信託登記を行う際には、金融機関や法務局の登記官も契約の有効性を確認します。本人が既に認知症であると疑われる場合、契約の効力がないと判断されて手続きが進められないことがあります。
裁判所による最終判断
最終的に争いが起きた場合、契約の有効性を判断するのは裁判所です。たとえば、相続人の一部が「信託契約は親が認知症の状態で結んだものだから無効だ」と主張すれば、裁判所が意思能力の有無を判断します。医師の診断記録や契約当時の状況が証拠として扱われます。
認知症と契約無効のリスク
実務では、認知症の診断を受けてから「まだ軽度だから大丈夫」と考えて契約を試みる方が少なくありません。しかし、公証人は契約時に本人の意思能力を確認するため、判断力に疑義がある場合は契約を成立させません。結果として、家族信託や遺言などの有効な手段を選べず、法定後見制度しか残されないという状況に陥ります。法定後見制度は財産保全の役割を果たしますが、自由度が低く、後見人への報酬が発生するなど、家族にとっては大きな負担になり得ます。
認知症の進行度と契約可能性
認知症の進行は段階的に現れます。初期段階であれば本人の判断力がある程度保たれているため、公証人も契約の意思を確認できる可能性があります。しかし、中期から重度に進むと日常生活に必要な判断すら困難となり、契約は無効とされます。以下の表は進行度と契約可能性の目安です。
| 認知症の状態 | 契約可能性 | 説明 |
|---|---|---|
| 診断前・正常 | 高い | 意思能力が十分に認められる |
| 軽度認知症(MCIなど) | 限界的 | 契約内容を理解できる場合に限り可能だが、公証人の判断次第 |
| 中期以降の認知症 | ほぼ不可能 | 判断力が失われ、契約は無効と判断される |
家族信託の有効性と民法の限界
民法の契約解釈に基づくと、認知症が進んでからの家族信託は不可能です。だからこそ、認知症になる前、あるいは軽度のうちに契約を結ぶ必要があります。家族信託は、委託者が元気なうちに「誰に財産を管理してもらうか」「将来どのように承継させるか」を具体的に定める制度であり、意思能力がある段階でしか成立しません。
専門家に相談する重要性
家族信託は法律や税務、家族関係にまたがる複雑な制度です。私、横手彰太としても強調したいのは、正しい知識と専門家のサポートがなければ、かえって失敗や無効契約のリスクが高まるという点です。
家族信託契約は、長期にわたる財産管理を可能にするため、契約締結時の意思能力が特に厳しくチェックされます。軽度認知症であっても、公証人が「内容を理解できていない」と判断すれば契約は成立しません。つまり、「認知症になってからでも間に合う」という考えは危険であり、元気なうちに契約を結ぶことが必須なのです。
本人と家族にとって最良の形を作るためには、早めに専門家とともに設計することが欠かせません。
まとめ
認知症になってからでは、民法上の意思能力の要件を満たせず、契約は無効となる可能性が極めて高いのが現実です。「まだ大丈夫」と思っている段階でこそ行動することが、財産を守り、家族を守る最善の方法です。少しでも親の認知症が心配な方は、早めに無料相談をお申し込みください。家族信託の正しい知識を持ち、状況に応じた最適な対策を一緒に考えていきましょう。