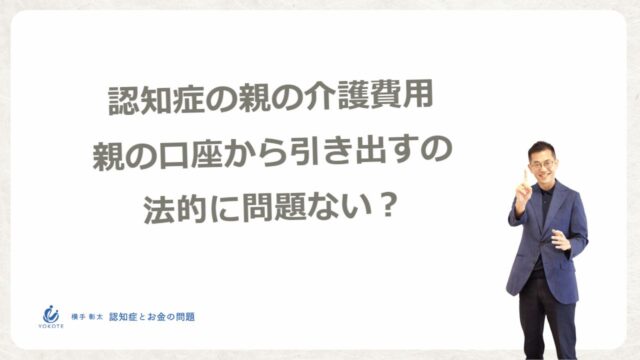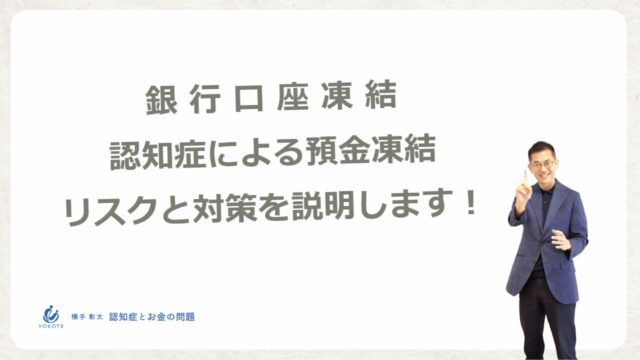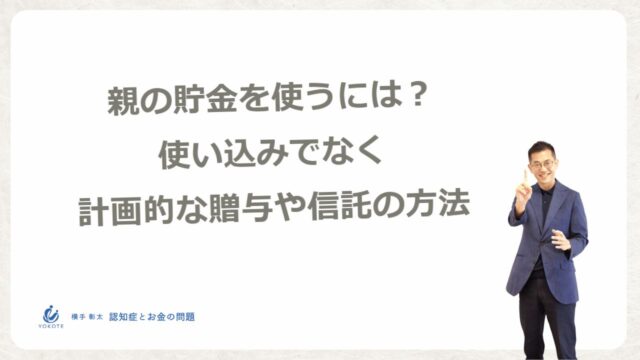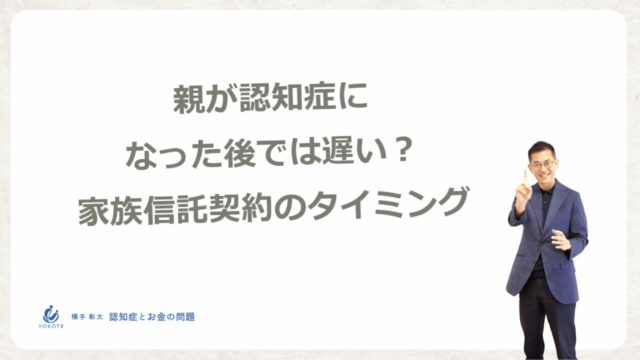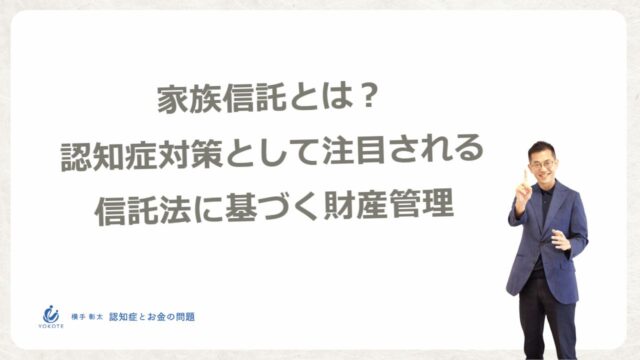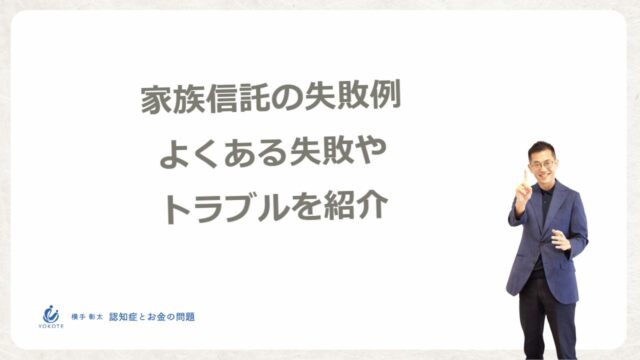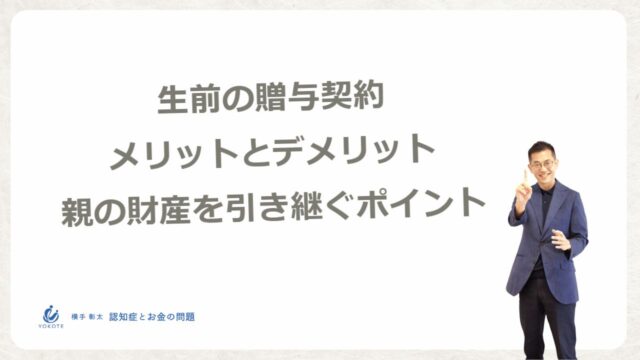認知症で長生きしすぎる時代、介護などのお金は誰が出す?
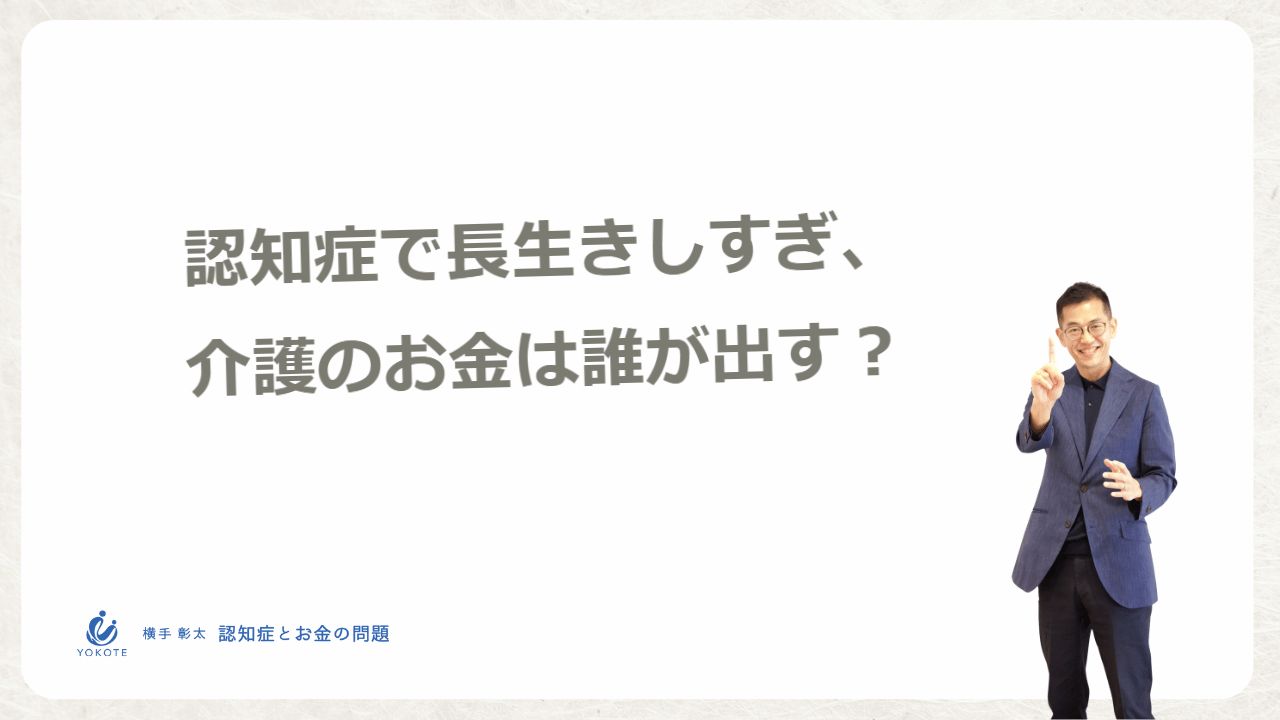
平均寿命が延びる一方で、認知症になってからの期間も長くなる「長生きリスク」が現実味を帯びています。親には十分な預貯金があるのに、本人が認知症になって口座が事実上動かせなくなり、結果として子どもが介護費用を立て替えるというケースは、私が相談を受ける中でも増えています。
しかも、いったん認知症が進むと、介護は数か月ではなく数年単位で続くため、家族の家計に重くのしかかります。
この記事では日本の制度の現実、親のお金を勝手に使ってトラブルになった典型例、そして、私、横手が提案している「使えるようにしておく仕組み」の考え方を整理していきます。
この記事の筆者
認知症とお金の専門家・横手彰太。これまでに家族信託の締結サポートは累計350組以上、信託財産総額180億円超を担当してきました。
日本全国67ヶ所の公証役場での手続き実績があり、NHK「クローズアップ現代+」やAERA、プレジデント、日本経済新聞など多数メディアでも紹介されています。セミナー講師としても300回以上登壇し、一般のご家庭から税理士、不動産会社まで幅広い方々にお金と認知症対策について解説してきました。著書に『親が認知症になる前に知っておきたいお金の話』をはじめ計5冊があります。

親が認知症になると、財産管理や相続の問題が一気に複雑化します。
だからこそ、「備えるなら今」が大切です。親に認知症の症状がある場合はすぐに対策しないと後悔しますので無料相談をお申し込みください。家族信託を詳しく学びたい方は2時間以上の濃い内容で解説した特別YouTube動画もご案内していますので、ぜひ最後までご覧ください。
認知症とお金の問題は、本当に重要な問題です。
手遅れになる前に、しっかりと考えて行動しましょう。
なぜ「お金はあるのに使えない」事態が起きるのか
認知症が進むと、本人が銀行窓口やオンラインバンキングで手続きをすることが難しくなります。
金融機関は本人の意思確認がとれない場合に払い戻しを拒むため、通帳と印鑑が目の前にあっても家族が自由にお金を動かせなくなります。本来は本人の生活や介護のために使ってよいはずの資金が、手続き上の理由で止まってしまうのです。
成年後見制度を申し立てれば使えるようにはなりますが、裁判所の監督が入り、支出目的が生活費や医療費に限られやすく、孫への援助や自宅のリフォームなど柔軟な支払いが難しくなります。その結果、現場では「とりあえず今月は子どもが払っておく」状態が続き、後から誰がいくら負担したのか分からなくなることが少なくありません。
介護費用はどのくらいかかるのか
自宅での訪問介護中心の生活なら毎月の自己負担は比較的抑えられますが、要介護度が上がってデイサービスやショートステイを組み合わせると月数万円の自己負担になることがあります。
さらに施設に入所すれば、特養であっても居住費・食費の自己負担があり、民間の有料老人ホームなら月15万〜20万円台になることも珍しくありません。
近年は健康寿命という概念も注目されていて、何歳まで自分で身の回りのことができるのかが重要視されていますが、体が弱って歩いたりできなくなるならば、意思疎通やお金の管理はまだ猶予期間があるのでお金の問題が顕在化しにくいのですが、認知症となると意思能力に効力がなくなり、契約や財産管理などの行為そのものが行えなくなるので、本人の意思決定やお金の面で問題が起きやすいのです。
認知症で10年生きるとすれば、家族の負担は合計で数百万円から1,000万円近くに達することもあり、誰がいつ払うかを決めないまま始めてしまうと後から兄弟間で揉める原因になります。
公的な軽減制度はあるが「ゼロ」にはならない
日本には介護保険があり、介護保険サービスの場合は原則1割負担(所得により2割・3割)でサービスを利用できます。また、施設入所などで費用が高額になる場合には「負担限度額認定」を受けることで食費や居住費が軽減される場合があります。
所得や預貯金が少ない高齢者であれば、これらの制度を使うことで月数万円程度に抑えられることもあります。ただし、これはあくまで「本人の収入・資産が少ない場合」の話であり、一定の年金や不動産、配当などの所得があり、預貯金もあるという人は対象外になることが多く、結局は本人の資産から払うべきという結論に戻ってきます。
ところがその本人資産が認知症のために動かしづらいことが、この問題をややこしくしているのです。
認知症の親のお金を勝手に使ってトラブルになったケース
実務でよく見るのは、同居しているきょうだいの一人が親のキャッシュカードを預かり、介護の実費も含めて使っていたところ、後から別のきょうだいが「本当に介護に使ったのか」「使い込みではないのか」と疑義を呈するケースです。
介護をしている側からすれば、病院へのタクシー代、オムツ代、デイサービスの追加費用、冷暖房費など細かい支出があって当然だと感じていますが、記録を残していないと説明が難しくなります。悪意がないのに「勝手に引き出した」と見られて親族関係が悪化するのは、横手さんがしばしば「一番もったいない」と表現するところです。本来なら親のお金を親のために使っただけなのに、仕組みがなかったためにトラブルになるのです。
誰が介護費用を出すのかを整理する視点
介護の費用負担を考えるときは、感情論よりも先に、誰の財布から何を払うのかを最初に決めておくと混乱が少なくなります。私、横手は「お金の出口を先に決めておく」ことを提案しています。親の資産から払うのか、子どもが一時的に立て替え後で精算するのか、あるいは家族信託で受託者が管理して払うのかという経路を明確にしておくと、後から「勝手に使った」と言われにくくなります。
介護費用の支払いパターンの比較
| 支払いパターン | 特徴 | 起こりやすいトラブル |
|---|---|---|
| 親の口座から直接支払う(認知症前に手続き済) | 本来最もわかりやすく公平。記録も残しやすい | 認知症後に手続きできないと口座が実質止まる |
| 子どもが立て替えて後で精算する | すぐに支払えるため現実的 | 領収書が残っていないと他のきょうだいに説明できない |
| 成年後見で支払う | 法的に最も安全で透明性が高い | 介護以外の支出がしにくく、継続的に報酬が発生する |
| 家族信託で受託者が支払う | 契約で目的を決めておけるので柔軟。子どもがやりやすい | 契約時に専門家費用がかかるが、長期で見ると合理的 |
この表から分かる通り、どの方法でもお金そのものは出ていきますが、後から揉めるかどうかは「事前にルールがあったかどうか」で変わります。
家族信託を使うと何が違うのか
家族信託は、親が元気なうちに「将来認知症になったらこの子に財産管理を任せる」「そのお金は介護や医療に使う」というルールを信託契約として残しておくものです。信託財産として分けておくことで、受託者になった子どもはその範囲で堂々と支払いができます。裁判所の許可をいちいち取る必要もなく、認知症になった後でも施設入居一時金や在宅介護の追加費用などをタイムリーに支払うことができます。横手さんがこの仕組みを強く勧めるのは、介護が始まると家族は「手続きしている暇がない」状態になるからです。前もってお金の出口を用意しておけば、介護そのものに集中できます。
成年後見との違い
成年後見制度の場合、本人の財産は「保全」が最優先されるため、介護以外の支出が非常にしにくくなります。さらに専門職後見人がつくと毎月数万円の報酬がかかり、長生きすればするほど固定的な出費になります。家族信託は最初に契約費用がかかるものの、あとは契約に従って家族が運用していけるため、長期の介護が想定される場合には結果として合理的になることが多いです。
それでも公的制度は確認しておく
本人にほとんど所得がない、年金が少ないという場合には、市区町村で「介護保険負担限度額認定」を受けることで施設の食費や居住費が軽減されることがあります。
また医療と介護が重なって負担が増える場合には高額介護サービス費の対象になることもあります。こうした公的な軽減策を使ってもなお足りない分を、信託口座や本人の預貯金から計画的に出していくという考え方にすると、家族の持ち出しが最小限で済みます。
まとめ
「認知症で長生きすること」が珍しくなくなった今、問題は「介護が長く続くのにお金が引き出せない」ことにあります。親のお金を親のために使うという当たり前のことが、手続きの壁や制度の硬さでできなくなっているのが現状です。
私、横手が繰り返し伝えているように、親がまだ判断できるうちに家族信託や任意後見といった仕組みを作っておくと、実際に介護が始まったときに家族関係を壊さずに済みます。
介護費用は誰かが必ず払います。だからこそ「誰のお金で、どの口座から、どんな目的で支払うのか」を先に決めておくことが、この時代のいちばんの備えになります。