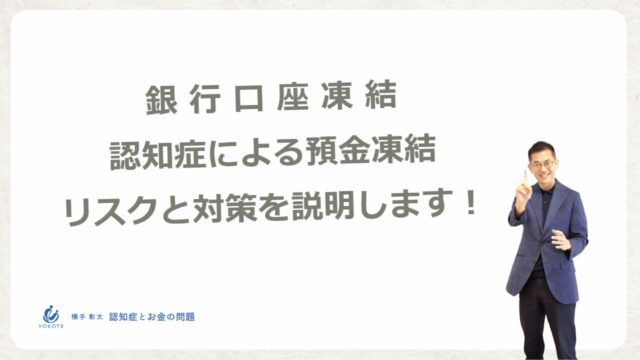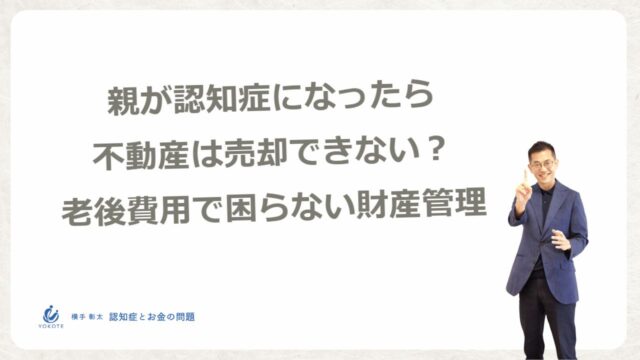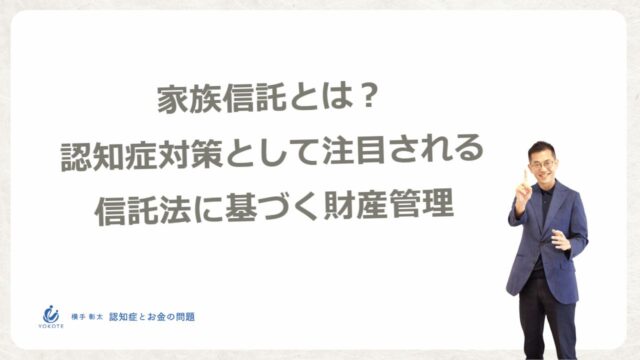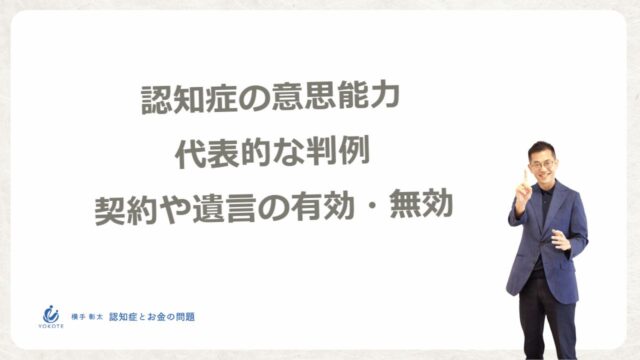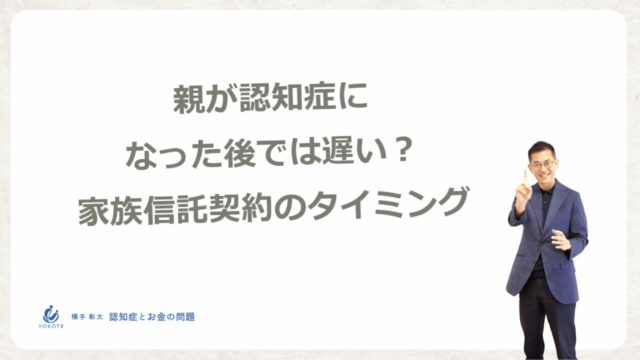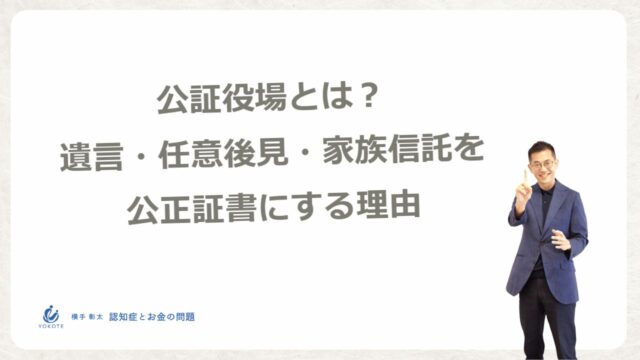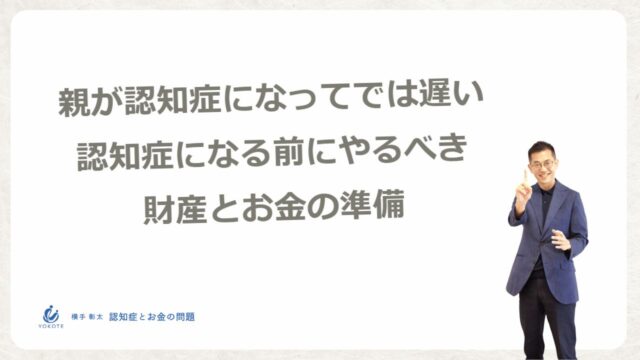認知症になる前に遺言書と家族信託を準備すべき理由
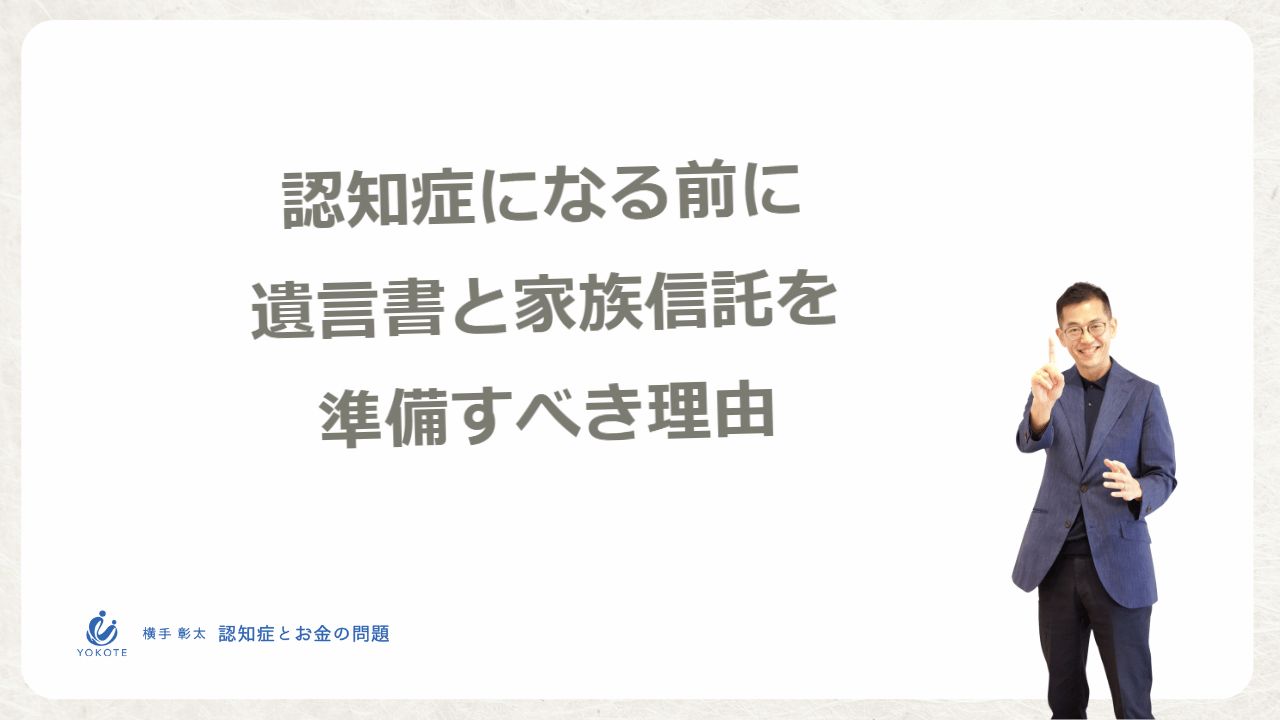
「母が認知症と診断された瞬間、通帳が使えなくなった」「施設に入りたいのに、不動産を売る手続きが進まない」――私、横手はこれまでに、そんなご家族の切実な声を何度も聞いてきました。
認知症によって判断能力が失われると、本人名義の財産は家族であっても自由に動かせなくなります。結果として、生活費が引き出せず、介護や医療の支払いにも支障が出ることがあるのです。
しかし、この問題は「認知症を発症する前」に備えることで防ぐことができます。
遺言書は亡くなった後の財産分配を定めるものですが、家族信託は生きている間に財産を守るための仕組みです。
この記事では、家族信託コンサルタントの私・横手彰太が、なぜ遺言と家族信託の両方を認知症になる前に準備すべきなのかを、具体的に解説していきます。
この記事の筆者
認知症とお金の専門家・横手彰太。これまでに家族信託の締結サポートは累計350組以上、信託財産総額180億円超を担当してきました。
日本全国67ヶ所の公証役場での手続き実績があり、NHK「クローズアップ現代+」やAERA、プレジデント、日本経済新聞など多数メディアでも紹介されています。セミナー講師としても300回以上登壇し、一般のご家庭から税理士、不動産会社まで幅広い方々にお金と認知症対策について解説してきました。著書に『親が認知症になる前に知っておきたいお金の話』をはじめ計5冊があります。

親が認知症になると、財産管理や相続の問題が一気に複雑化します。
だからこそ、「備えるなら今」が大切です。親に認知症の症状がある場合はすぐに対策しないと後悔しますので無料相談をお申し込みください。家族信託を詳しく学びたい方は2時間以上の濃い内容で解説した特別YouTube動画もご案内していますので、ぜひ最後までご覧ください。
認知症とお金の問題は、本当に重要な問題です。
手遅れになる前に、しっかりと考えて行動しましょう。
認知症とお金の問題は「ある日突然」始まる
私、横手はこれまで数多くのご家族から、認知症による「お金の問題」の相談を受けてきました。
多くのケースでは、「まだ大丈夫だろう」と思っていた矢先に、親が銀行や不動産の手続きができなくなり、家族全体が困るという現実に直面しています。
日本では高齢者の約5人に1人が認知症になるといわれており、その数は今後さらに増える見込みです。認知症になると、本人の判断能力が低下し、財産の管理や契約行為ができなくなります。つまり、たとえ家族であっても、勝手に通帳からお金を引き出したり、不動産を売却したりすることはできません。
この「判断能力の喪失」が、家族のお金の流れを止めてしまう最大の原因です。
だからこそ、認知症になる前に、自分の意思で財産を託す仕組みを作っておくことが極めて重要なのです。
遺言書は「死後の準備」、家族信託は「生前の仕組み」
私が多くの現場で感じるのは、「遺言書を作っておけば安心」と誤解している方が非常に多いということです。
確かに遺言書は、自分が亡くなった後の財産の分け方を明確にして、家族の争いを防ぐための大切な手段です。しかし、遺言書には「生きている間の財産管理を託す力」はありません。
認知症の進行によって判断能力が失われると、遺言書があっても、生前の資産運用や生活費の出金などが止まってしまうのです。
一方で、「家族信託」は、判断能力があるうちに自分の財産を信頼できる家族に託し、管理や運用を任せることができる仕組みです。遺言が“死後の分配”を目的としているのに対し、家族信託は“生前の管理”を目的としているという違いがあります。
| 仕組み | 財産を管理できる時期 | 主な目的 | 契約の形式 |
|---|---|---|---|
| 遺言書 | 死後のみ有効 | 相続の分配 | 公正証書遺言・自筆証書遺言など |
| 家族信託 | 生前から有効 | 財産管理・生活支援・相続対策 | 信託契約(公正証書にすることが多い) |
このように、遺言と家族信託は「どちらか一方」ではなく、「両方を組み合わせて準備する」ことで、はじめて安心できる老後と相続の設計が完成します。
認知症になるとできなくなること
私、横手は常に「今できることは、今しかできない」とお伝えしています。
認知症を発症すると、本人の意思を確認できない状態になるため、契約行為ができなくなります。すると、次のような問題が起こります。
これらは決して特殊な例ではありません。
私の相談事例でも、親が認知症と診断された瞬間から、家族全員が「もう遅かった」と気づくケースが非常に多いのです。
家族信託は「家族で支える」ための仕組み
家族信託とは、本人(委託者)が信頼できる家族(受託者)に財産の管理や運用を任せる契約です。
これは単なる財産の「名義変更」ではなく、「管理権限の移行」です。たとえば、親が持っている自宅や預金を息子や娘に信託しておけば、親が認知症になっても、その子どもが生活費を出したり、施設費を支払ったりすることが可能になります。
私、横手はこの仕組みを「家族の中でお金の流れを止めない仕組み」と呼んでいます。
成年後見制度のように裁判所の監督を受けずに、柔軟に家族で資産を守り運用できることが、家族信託の最大の魅力です。
ただし、信託契約は本人の意思が明確なうちにしか結ぶことができません。
「親が認知症と診断されたから家族信託を結びたい」という相談も多く寄せられますが、その時点ではもう公正証書での信託契約が難しくなります。
ですから、信託の準備はまだ元気なうちに行うことが絶対条件です。
関連記事:親が認知症になった後では遅い?信託契約の限界とタイミング
遺言書と家族信託を併用することで「生前・死後の両方」を守れる
家族信託は生前の財産管理に強い一方で、信託契約の中で「信託財産の帰属先」を決めておかなければ、死後の相続に関しては別途手続きが必要になる場合もあります。
そこで、私、横手は実務上、「遺言書」と「家族信託」を併用する形をおすすめしています。
生前は家族信託によって生活費や資産をスムーズに管理し、死後は遺言書によって相続の分配を明確にする。この二つをセットで準備しておくことで、「認知症による財産の凍結」と「相続後の争い」という二つの大きなリスクを同時に防ぐことができます。
公証役場で家族信託契約と遺言書を公正証書にしておけば、形式上の不備によって無効になる心配もなく、家族全員が安心して将来の計画を立てられます。
関連記事:公証役場とは?遺言・任意後見・家族信託を公正証書にする理由
私が伝えたいこと――「準備は、まだ元気なうちに」
私が相談を受けるご家族の中には、「もっと早くやっておけばよかった」という後悔の言葉を口にされる方が本当に多くいます。
認知症の問題は、発症してからではもう手遅れです。
遺言書も、家族信託も、「自分の意思を形にできるうち」にこそ意味があります。
家族の中でお金の流れを止めず、本人の想いをしっかりつなぐために。
私は、遺言と家族信託を「老後のダブルセーフティネット」として、できる限り早く整えておくことを強くお勧めしています。
まとめ
認知症は誰にでも起こり得る現実であり、「まだ大丈夫」と思っているうちが、一番危険な時期です。
遺言書で死後の想いを残し、家族信託で生前の財産を守る。
その二つの準備が、あなたと家族の未来を守る最善の一歩になると、私、横手は確信しています。