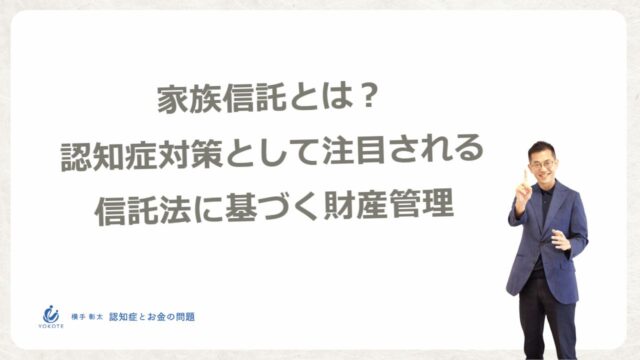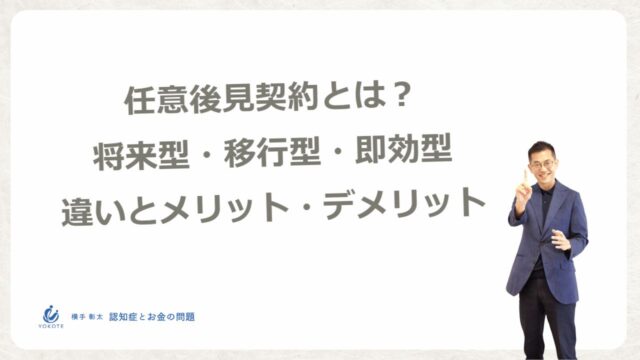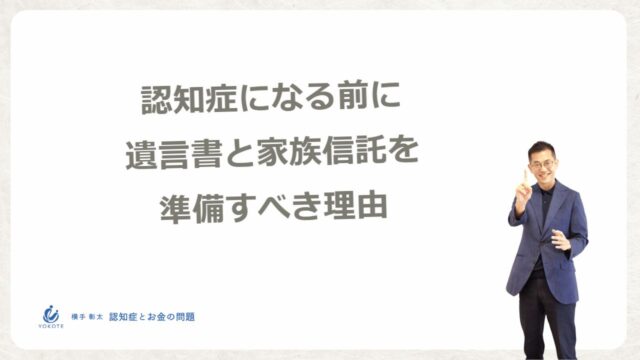親が認知症になったら…じゃない、認知症になる前にやるべきこと
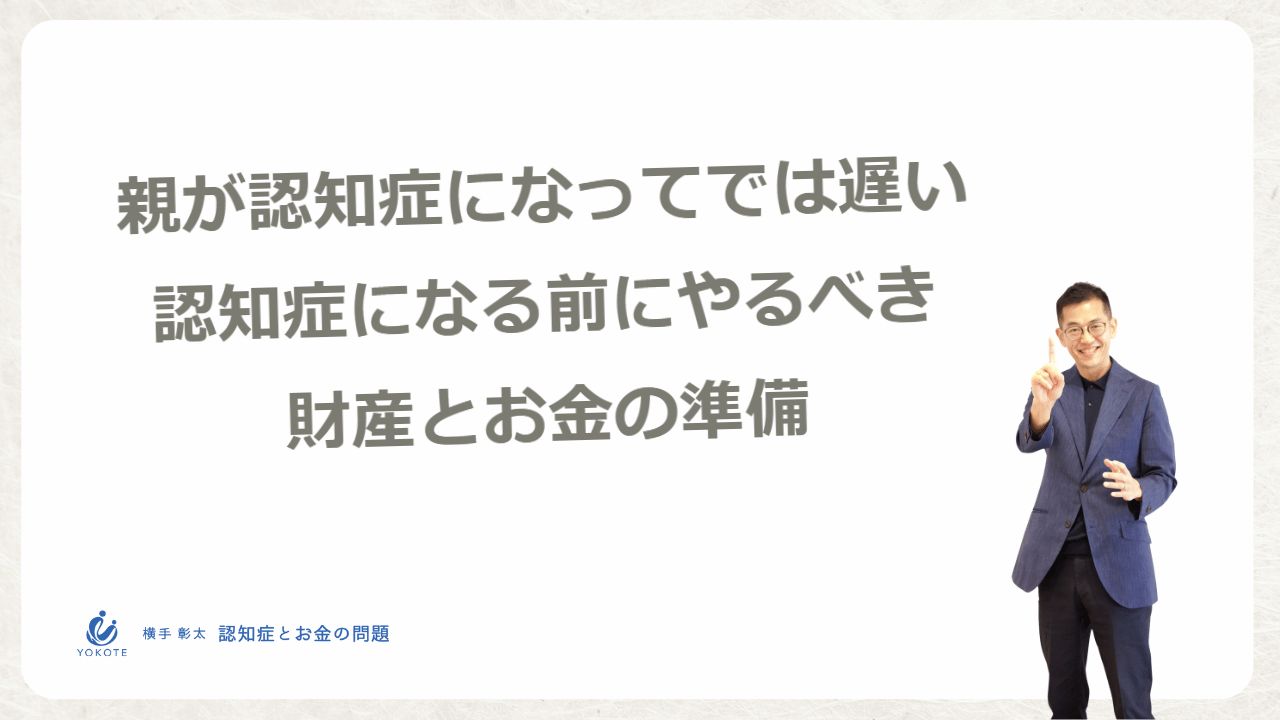
「親が認知症になったら、どうしよう」――私、横手はこの言葉を何度も聞いてきました。
しかし、実際には“認知症になった後”ではもうできないことがたくさんあります。銀行の口座は凍結され、不動産も動かせず、介護施設への入居費用を準備することさえ難しくなる。つまり、認知症はお金の問題でもあるのです。
だからこそ大切なのは、「親が認知症になったら」ではなく、「なる前に」備えること。
この記事では、家族信託コンサルタントの私・横手彰太が、認知症とお金の現実を踏まえながら、今からできる財産管理・家族信託・遺言書の準備について詳しくお伝えします。
この記事の筆者
認知症とお金の専門家・横手彰太。これまでに家族信託の締結サポートは累計350組以上、信託財産総額180億円超を担当してきました。
日本全国67ヶ所の公証役場での手続き実績があり、NHK「クローズアップ現代+」やAERA、プレジデント、日本経済新聞など多数メディアでも紹介されています。セミナー講師としても300回以上登壇し、一般のご家庭から税理士、不動産会社まで幅広い方々にお金と認知症対策について解説してきました。著書に『親が認知症になる前に知っておきたいお金の話』をはじめ計5冊があります。

親が認知症になると、財産管理や相続の問題が一気に複雑化します。
だからこそ、「備えるなら今」が大切です。親に認知症の症状がある場合はすぐに対策しないと後悔しますので無料相談をお申し込みください。家族信託を詳しく学びたい方は2時間以上の濃い内容で解説した特別YouTube動画もご案内していますので、ぜひ最後までご覧ください。
認知症とお金の問題は、本当に重要な問題です。
手遅れになる前に、しっかりと考えて行動しましょう。
「親が認知症になったらどうしよう」では、もう遅い
私、横手はこれまで数百件を超える家族信託や相続の相談を受けてきました。その中でいつも感じるのは、多くの人が「親が認知症になったらどうしよう」と起きてからの対策を考えているということです。
けれど、認知症の問題は起きてからでは対策できません。
なぜなら、認知症を発症して判断能力が低下すると、法律上、本人は「契約ができない人」とみなされるからです。つまり、親が認知症になってからでは、家族信託も、遺言書の作成も、財産の名義変更も一切できなくなります。
私のところにも「母が認知症になってから信託契約をしたい」と相談に来られる方がいますが、その時点でできるのは成年後見制度の利用しかありません。しかし成年後見制度には、裁判所の監督や定期報告など、本人・家族双方にとって大きな負担が伴います。だからこそ、「親が認知症になったら」ではなく、「なる前に」こそ動くべきなのです。
認知症とお金の問題は、なぜ深刻なのか
認知症は医療や介護の問題と思われがちですが、私が最も深刻だと感じているのは「お金の問題」です。
親が認知症になると、銀行は本人以外の取引を原則として認めません。たとえ家族でも、委任状を持っていても、判断能力がないと判断されれば口座は凍結されてしまいます。
また、不動産の売却や賃貸契約もできなくなり、介護施設の入居費用を捻出するために家を売りたくても、本人が署名できないために手続きが進まない。これが、現実に起こっている「認知症とお金の問題」です。
私、横手はこれを「家族のお金が止まる瞬間」と呼んでいます。
介護費が払えず、子どもが立て替える。貯金があっても動かせない。そんな理不尽な状況が、準備不足によって生まれてしまうのです。
家族信託で「お金の流れを止めない」
この問題を解決する手段として、私が最も重視しているのが「家族信託」です。
家族信託とは、親(委託者)が自分の財産を信頼できる家族(受託者)に託し、管理や運用を任せる契約のことです。信託を設定しておけば、親が認知症になっても、家族が代わりに財産を動かすことができます。
たとえば、親が所有する自宅を信託財産として子どもが管理すれば、施設入居時に自宅を売却して費用に充てることもできます。また、信託口口座(信託専用の銀行口座)を開設しておけば、親の生活費や介護費を家族がスムーズに支払うことも可能です。
この仕組みの大きな特徴は、成年後見制度のように裁判所の監督を受けずに、柔軟に家族で財産を動かせる点にあります。
私、横手はよく「家族信託は家族が自分たちの力で家族を守るための制度です」とお伝えしています。
遺言書は「死後の備え」、信託は「生前の仕組み」
多くの方が「遺言書を書けば安心」と考えていますが、遺言書は死後の相続分配を決めるものであり、生きている間の財産管理には使えません。
つまり、認知症によって判断能力を失ってしまうと、遺言書があっても生活費を出したり、不動産を処分したりすることはできないのです。
家族信託は、この生前の管理を補うための仕組みです。
親が元気なうちに信託契約を結んでおくことで、認知症が進行した後も、家族が本人の生活や介護を支えるために資産を安全に活用できます。
私は実務の現場で、遺言書と家族信託を「両輪の備え」として組み合わせるケースを多く見ています。遺言は死後の分配、信託は生前の管理。この二つが揃ってこそ、本当の意味で家族を守る“終活の完成形”になるのです。
「まだ大丈夫」と思う人ほど危ない
相談に来られるご家族の多くは、「うちの親はまだしっかりしているから」と言われます。
しかし、認知症はある日突然、進行が加速します。昨日まで普通に会話していたのに、今日からは意思確認ができなくなる――そんな変化を、私は何度も目の当たりにしてきました。
信託契約や遺言書の作成には、本人の「判断能力」が不可欠です。つまり、「まだ大丈夫」と思っているうちにしか、できない準備なのです。
私は常に、「判断能力は資産と同じくらい大切な財産です」とお伝えしています。
どれだけ財産があっても、判断能力を失えばそれを守る手立てはなくなります。
認知症になる前にやるべき3つの準備
認知症への備えというと、「介護保険」「施設探し」を思い浮かべる方が多いですが、本当に必要なのは「財産を守る仕組みづくり」です。
私が実務で提案している主な準備は、次の3つです。
家族信託の設計(生活資金・不動産・口座を信託して、家族で管理)
家族信託は、生前の管理を補うための仕組みで、親が元気なうちに信託契約を結んでおくことで、認知症が進行した後も、家族が本人の生活や介護を支えるために資産を安全に活用できます。
遺言書の作成(死後の分配を明確にして、相続トラブルを防ぐ)
遺言書は、死後の相続分配を決めるもので、あらかじめ準備しておくことで、相続のトラブルを防ぐことができます。
任意後見契約の検討(将来、判断力が落ちたときのバックアップ契約)
「任意後見契約」とは、自分が元気なうちに、将来判断能力が衰えたときに備えて、誰にどんなサポートをお願いするのかをあらかじめ自分の意思で決めておく契約です。
家庭裁判所が決める法定後見と違い、任意後見は本人が自ら信頼できる人を後見人に選び、内容を細かく設計できる点が最大の特徴です。
この3つを公正証書にしておけば、形式の不備で無効になる心配もなく、銀行や行政手続きでも信頼性が高い書類として扱われます。
「家族の安心」は、親が元気なうちにしか作れない
私は、家族信託の現場で何度も「もっと早く知りたかった」という言葉を聞いてきました。
認知症の問題は、誰にでも起こり得ます。そして、その時になって初めて「準備しておけばよかった」と気づくのです。
でも、そのときにはもう、できない手続きがたくさんあります。
だからこそ、「親が認知症になったら」ではなく、「認知症になる前に」。
家族が元気なうちに、話し合い、決めて、形にしておくことが、家族を守る何よりの思いやりなのです。
私、横手はこれからも「お金の流れを止めない」ための実践的な支援を通して、家族の安心を形にするお手伝いを続けていきたいと考えています。
まとめ
認知症対策の本質は「介護の準備」ではなく「お金の準備」です。
家族信託で生前の財産を守り、遺言書で死後の想いを伝える。
この二つを整えることが、「親が認知症になっても困らない家族」をつくる最善の方法です。
そしてその準備は、今しかできません。