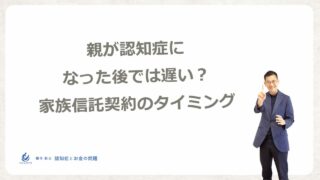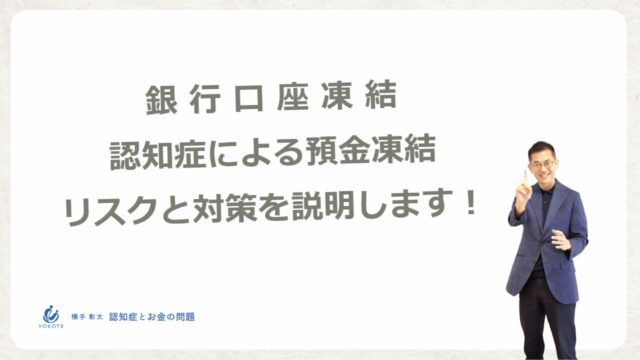親の将来の介護や相続を見据えて準備を始めたいと思っても、「まだ元気だから大丈夫」と先延ばしにしてしまう方は少なくありません。しかし、認知症が進行して判断能力が失われてしまうと、家族信託契約は締結できなくなります。銀行口座の凍結や不動産の売却停止、介護費用の捻出困難など、避けられるはずの問題が一気に表面化する可能性もあります。
本記事では、家族信託の仕組みや認知症進行後のリスク、契約が可能な限界と最適なタイミングについて詳しく解説します。
この記事の筆者
認知症とお金の専門家・横手彰太。これまでに家族信託の締結サポートは累計350組以上、信託財産総額180億円超を担当してきました。
日本全国67ヶ所の公証役場での手続き実績があり、NHK「クローズアップ現代+」やAERA、プレジデント、日本経済新聞など多数メディアでも紹介されています。セミナー講師としても300回以上登壇し、一般のご家庭から税理士、不動産会社まで幅広い方々にお金と認知症対策について解説してきました。著書に『親が認知症になる前に知っておきたいお金の話』をはじめ計5冊があります。

親が認知症になると、財産管理や相続の問題が一気に複雑化します。
だからこそ、「備えるなら今」が大切です。親に認知症の症状がある場合はすぐに対策しないと後悔しますので無料相談をお申し込みください。家族信託を詳しく学びたい方は2時間以上の濃い内容で解説した特別YouTube動画もご案内していますので、ぜひ最後までご覧ください。
認知症とお金の問題は、本当に重要な問題です。
手遅れになる前に、しっかりと考えて行動しましょう。
家族信託の仕組みと役割
家族信託とは、親(委託者)が将来に備えて、自分の財産の管理や処分を信頼できる家族(受託者)に託す制度です。法律上は「信託法」に基づいて契約が行われ、委託者が生存中も亡くなった後も、受託者が契約内容に従って財産を管理・運用・処分します。信託の対象となる財産は、不動産、預貯金、有価証券など多岐にわたり、契約によって管理方法や使い道を詳細に定められるため、将来の介護費用の確保や相続の円滑化に直結します。
特に民法に基づく遺言や後見制度と異なり、信託契約は「財産管理」と「承継の指定」を一体的に行える点が大きな特徴です。遺言は原則として死後に効力が発生しますが、信託は生前から効力を持たせることができるため、親の判断能力が低下しても契約に基づいた財産運用を継続できます。
家族信託をしないまま認知症が進行した場合のリスク
| 分野 | 起こる事態 | 具体的な影響 |
|---|---|---|
| 銀行口座 | 本人の判断能力が疑われると凍結され、入出金ができなくなる | 介護費や医療費、生活費の支払いが滞り、家族が立て替えざるを得なくなる |
| 不動産 | 売却や賃貸契約などの処分行為ができなくなる | 空き家や土地を活用できず、固定資産税や維持費だけが発生し続ける |
| 資産運用 | 株式や投資信託などの売買や管理ができなくなる | 市場の変動に対応できず、資産価値の下落や機会損失が生じる |
| 介護資金 | 不動産や預金を換金できず、資金化が困難になる | 高額な施設入居や在宅介護の費用を捻出できず、介護の質が低下する可能性がある |
| 家族関係 | 財産管理や介護負担を巡って家族間で対立が起きやすくなる | 相続時に不公平感が残り、人間関係が長期的に悪化する |
認知症が進行すると、財産管理に必要な意思能力が失われ、日常的な資金の引き出しや資産運用が著しく制限されます。銀行は名義人の判断能力に疑義がある場合、トラブル防止のために口座を凍結します。この結果、介護サービスや施設入居費、医療費の支払いが滞る恐れがあります。
また、不動産の売却や賃貸契約には所有者の署名や押印が必要となりますが、判断能力が低下した状態では契約自体が無効とされる可能性が高くなります。資産価値が高い不動産を保有していても、それを換金して介護資金に充てることができず、結果として家族が高額な立替を余儀なくされる事態も発生します。
さらに、財産の管理を巡る家族間の感情的な対立が深刻化する傾向があります。特定の子どもが費用を負担しても、後に相続分で不公平感が残るなど、長期的な人間関係の悪化につながることもあります。
認知症の進行と契約締結の限界
家族信託の契約は、委託者が契約の目的や内容を理解し、合理的な判断を下せる「意思能力」を有していることが条件です。意思能力は法律上明確な数値基準ではなく、医師の診断や公証人の面前での確認によって総合的に判断されます。
認知症の進行度と家族信託契約の可能性
| 認知症の進行度(目安) | 主な症状や状態 | 家族信託契約の可能性 |
|---|---|---|
| 正常または軽度認知障害(MCI) | 日常生活はほぼ自立、時々物忘れがあるが重要な判断は可能 | 契約可能。内容を理解できれば問題なく契約できる時期。最も望ましいタイミング |
| 初期認知症 | 会話や日常生活は概ね自立しているが、新しい情報の記憶に支障あり。意思表示は可能 | 契約可能だが要注意。公証人や医師の診断書で判断能力の確認が必要になるケースが多い |
| 中等度認知症 | 日常生活に部分的な介助が必要。時や場所の認識があいまい。契約の目的や内容の理解が困難 | 契約困難。意思能力が認められない可能性が高く、成年後見制度の利用を検討する段階 |
| 重度認知症 | 自分の名前や家族がわからない、会話が成り立たない。全般的な生活に介助が必要 | 契約不可。意思能力が欠如しており、家族信託は締結できない |
軽度認知障害(MCI)や初期の認知症であれば、本人が契約内容を理解し、意思表示できる場合には契約が可能なケースがあります。ただし、中等度以上の認知症では、契約の意味や効果を理解できないため契約は成立せず、この段階になると家族信託は選択肢から外れます。代替手段として成年後見制度を利用することになりますが、この制度では財産の処分や運用に制限が多く、柔軟な活用は困難です。
つまり、家族信託を検討できるタイミングは限られており、判断能力の残存期間は想像以上に短い可能性があるという現実を理解する必要があります。
最適な着手時期とその理由
信託契約の締結に適した時期は、親が元気で日常生活に支障がないうち、あるいは軽度の物忘れが見られ始めた段階です。この時期であれば、契約の意図や内容を十分に説明し、本人の意思を尊重した内容を盛り込むことができます。
着手を早めることで、契約書の作成、公証役場での認証、必要に応じた登記などを余裕を持って進められます。また、親が元気なうちに家族全員で財産の現状や将来の方針を共有できるため、将来的な争いの芽を事前に摘み取ることができます。
一方で、「まだ元気だから大丈夫」と考えて先送りすると、突然の入院や体調悪化、認知症の急速な進行によって意思能力が失われ、信託契約が締結できないまま財産が凍結されるリスクが高まります。
まとめ
家族信託は、認知症による財産凍結や資産活用の停止を防ぐ、極めて有効な制度です。しかし、契約には委託者の明確な意思能力が不可欠であり、進行した認知症では利用できません。判断能力が残っているうちに着手することが、将来の経済的安定と家族間の平穏を守る最も確実な方法です。
早期に行動することで、介護費用の確保、資産の有効活用、相続の円滑化といった複数の課題を同時に解決できます。「まだ大丈夫」と思っている今こそが、実は最も適したタイミングであることを意識することが重要です。