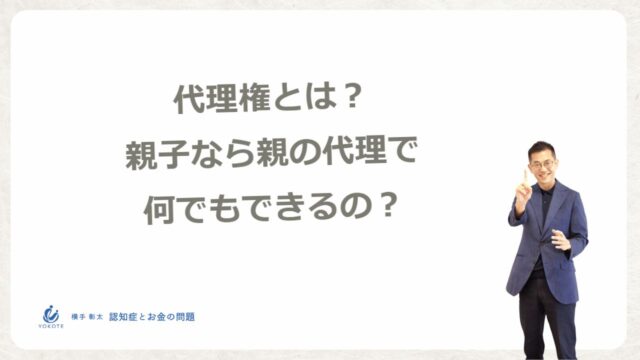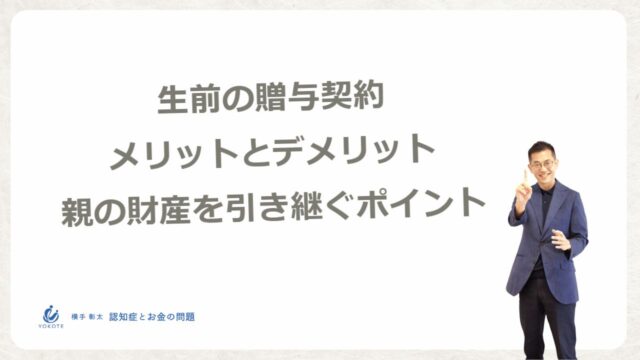親の貯金を安全に使うには?使い込みでなく計画的な贈与や信託の方法
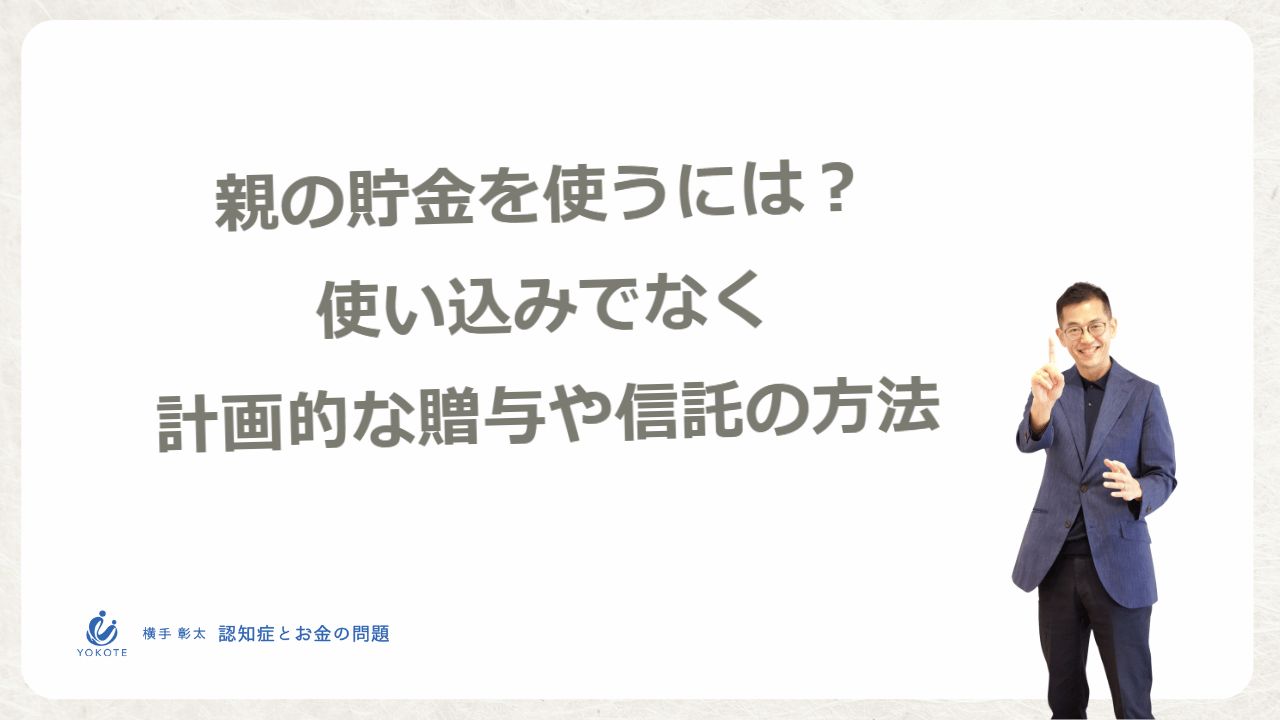
私、横手はこれまでに多くのご家族の相談を受けてきました。
その中でも特に深刻なのが、「親の介護や生活費のためにお金を使ったのに、兄弟から“使い込み”だと疑われた」というケースです。
ほとんどの方は、親のためを思って行動しています。
介護サービスの支払いや病院代、時には老人ホームの入居費など、誰かが立て替え、手続きを進めなければならない現実があります。
しかし、法律上・形式上は「親の財産を他人が動かした」という事実だけが残り、意図がどうであれ説明責任を求められることになるのです。
特に相続の場面では、「領収書がない」「記録がない」というだけで疑いが生まれ、結果的に兄弟の関係が壊れてしまうこともあります。
つまり、親のお金を安全に使うとは、「正しい手続きを経て、透明性を保つ」ということなのです。
この記事の筆者
認知症とお金の専門家・横手彰太。これまでに家族信託の締結サポートは累計350組以上、信託財産総額180億円超を担当してきました。
日本全国67ヶ所の公証役場での手続き実績があり、NHK「クローズアップ現代+」やAERA、プレジデント、日本経済新聞など多数メディアでも紹介されています。セミナー講師としても300回以上登壇し、一般のご家庭から税理士、不動産会社まで幅広い方々にお金と認知症対策について解説してきました。著書に『親が認知症になる前に知っておきたいお金の話』をはじめ計5冊があります。

親が認知症になると、財産管理や相続の問題が一気に複雑化します。
だからこそ、「備えるなら今」が大切です。親に認知症の症状がある場合はすぐに対策しないと後悔しますので無料相談をお申し込みください。家族信託を詳しく学びたい方は2時間以上の濃い内容で解説した特別YouTube動画もご案内していますので、ぜひ最後までご覧ください。
認知症とお金の問題は、本当に重要な問題です。
手遅れになる前に、しっかりと考えて行動しましょう。
法律上、親の貯金を家族が使うことは「原則できない」
まず前提として理解しておくべきなのは、家族であっても親の財産を勝手に動かす権限はないということです。
銀行口座の出金や契約行為は、原則として「本人の意思確認」が必要です。
親が認知症などで判断能力を失っている場合、委任状を作っても無効となり、銀行は出金を認めません。
| 状況 | 家族による出金の可否 | 理由 |
|---|---|---|
| 親が意思確認できる状態で委任している | 可能 | 本人の意思に基づく委任行為 |
| 親が認知症で判断能力を失っている | 不可 | 法的な意思表示ができないため |
| 家族が代理でATMやネットバンキングを使用 | 違法の可能性 | 利用規約違反・無権代理行為 |
つまり、「親のため」という理由では法律上の正当性は担保されません。
この点を誤解したままお金を動かしてしまうと、結果的に使い込みとみなされるリスクが生じるのです。
「使い込み」と「正しい支出」の境界線
私、横手が現場で見てきた事例では、同じ行為でもやり方によって評価がまったく異なることがあります。
たとえば、親の介護費を支払うために子が親の口座から出金した場合でも、
その記録を残し、領収書やメモで「どの支払いに使ったか」を明確にしていれば問題になりません。
しかし、同じ金額を「とりあえず現金で引き出して使った」だけでは、後から説明できず、相続時に疑念を生むのです。
つまり、何に使ったかを証明できる状態にしておくことが、使い込みを防ぐ最も確実な方法です。
参考:認知症の親の介護費用を親の口座から引き出すのは法的に問題ない?
親の貯金を使いこむことは罪に問われないことも多いが・・・
私、横手は現場で「兄が親の通帳を持っていて、勝手に使っているようだ」というご相談をよく受けます。
しかし実際のところ、親の貯金を家族が使い込んでも、刑事罰に問われないケースが多いのが現実です。
刑法上の横領罪は「他人の財産を不法に処分した場合」に成立しますが、親子などの親族間では刑事告訴がなければ立件されないという「親族相盗例(刑法第244条)」が適用されます。
つまり、たとえ家族が親の預金を勝手に使っても、警察が動かないことが多いのです。
しかし、罪に問われないからといって「問題がない」というわけではありません。
相続の段階で使途が不明な出金が発覚すれば、「使い込み」として民事上の返還請求を受けることがあります。
家族信託や任意後見契約を整えておけば、こうした疑念や争いを未然に防ぐことができるのです。
安全に親のお金を使うための3つの方法
私、横手は実務の中で、「親の財産を安全に使う」ための方法を3つに整理してお伝えしています。
| 方法 | 内容 | メリット |
|---|---|---|
| ① 贈与契約を明確にする | 親が元気なうちに、生活援助や介護費として贈与契約を交わす | 法的根拠が明確になり、贈与税の範囲も整理できる |
| ② 家族信託を活用する | 親が信頼できる家族に財産管理を託す契約を公正証書で作成 | 認知症後もお金を動かせ、介護費や生活費の支出が可能 |
| ③ 任意後見契約を結ぶ | 将来の判断力低下に備えて後見人を指定 | 家庭裁判所の監督下で法的に認められた支出ができる |
これらの仕組みはいずれも、「法的根拠をもって行動する」ためのものです。
特に家族信託は、親が認知症になった後でも生活資金の支出や不動産の売却が可能な点で、非常に実用的です。
参考:代理権とは?親子なら親の代理で契約も預金の移動も何でもできるの?
参考:親が認知症になった後では遅い?信託契約の限界とタイミング
家族信託で「親のお金を守りながら使う」
家族信託とは、親(委託者)が信頼できる家族(受託者)に財産を託し、管理や運用を任せる仕組みです。
契約を交わすことで、受託者には法律上の代理権が与えられます。
そのため、親が判断能力を失っても、受託者が銀行取引や支出を続けられるのです。
たとえば、老人ホームの入居一時金や介護費用を支払うために、信託口座から直接支出できるように設計しておけば、「使い込み」と誤解される余地がなくなります。
さらに、家族信託契約には「親のためにのみ使う」「支出内容を定期的に報告する」などの条項を設けることができるため、透明性を保ちながら安心して管理ができます。
「親の貯金」は家族の共有財産ではない
私、横手は記事や講演でも繰り返しお伝えしています。
「親のお金は親のものであり、家族の共有財産ではない」という基本を忘れてはいけません。
家族が管理すること自体は悪いことではありませんが、本人のために、本人の意思を尊重しながらという原則を外れるとトラブルになります。
逆に、法的な手続きを踏んで透明性を保てば、家族間の信頼を守りながら円滑な介護・生活支援ができます。
親の貯金を「守りながら使う」ことが本当の思いやり
親の貯金を安全に使うために必要なのは、「感情」ではなく「仕組み」です。
勝手に出金することは、親のためであってもリスクになります。
しかし、家族信託や贈与契約などを活用すれば、法的にも安全で、家族全員が納得できる形でお金を動かすことができます。
私、横手はいつもこう伝えています。
「親の財産を守ることと、親のために使うことは、両立できる」――。
正しい準備をすれば、使い込みの不安も、相続の争いも防ぐことができるのです。