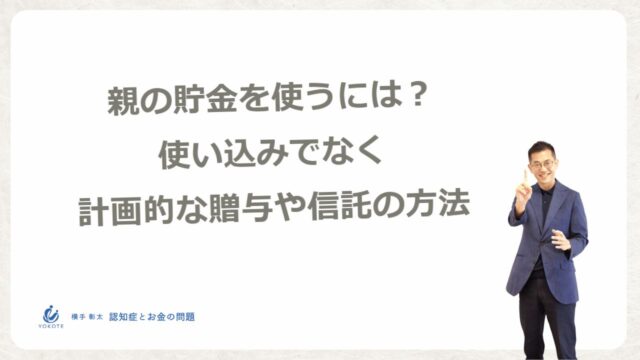生前の贈与契約のメリットとデメリット、親のお金や不動産を引き継ぐポイント

私、横手は多くのご家族から「親が元気なうちに、財産を子どもに贈与しておきたい」という相談を受けてきました。
その背景には、「相続でもめたくない」「介護や生活を支えてくれている子に早めに渡したい」という親心があります。
確かに、生前の贈与には相続対策や家族間の公平性の確保など、多くのメリットがあります。
しかし一方で、贈与契約を安易に結ぶと「税務上のトラブル」や「老後資金の不足」「家族間の不信感」などの問題を引き起こすこともあります。
生前贈与は、感情ではなく法的・実務的にどう仕組むかを理解して行うことが重要です。
この記事では、家族信託コンサルタントである私・横手彰太が、贈与契約の基本とその注意点を、現場での経験を交えて解説していきます。
この記事の筆者
認知症とお金の専門家・横手彰太。これまでに家族信託の締結サポートは累計350組以上、信託財産総額180億円超を担当してきました。
日本全国67ヶ所の公証役場での手続き実績があり、NHK「クローズアップ現代+」やAERA、プレジデント、日本経済新聞など多数メディアでも紹介されています。セミナー講師としても300回以上登壇し、一般のご家庭から税理士、不動産会社まで幅広い方々にお金と認知症対策について解説してきました。著書に『親が認知症になる前に知っておきたいお金の話』をはじめ計5冊があります。

親が認知症になると、財産管理や相続の問題が一気に複雑化します。
だからこそ、「備えるなら今」が大切です。親に認知症の症状がある場合はすぐに対策しないと後悔しますので無料相談をお申し込みください。家族信託を詳しく学びたい方は2時間以上の濃い内容で解説した特別YouTube動画もご案内していますので、ぜひ最後までご覧ください。
認知症とお金の問題は、本当に重要な問題です。
手遅れになる前に、しっかりと考えて行動しましょう。
贈与契約とは?口約束でも成立するが証拠が必要
贈与契約とは、一方(贈与者)が自分の財産を無償で他人(受贈者)に与える意思を示し、それを相手が受け入れることで成立する契約です(民法第549条)。
つまり、贈与は「もらう側が承諾すれば成立」します。
ただし、口頭でも成立しますが、後から「そんな話はしていない」と争いになるケースが多いため、実務上は書面で明確に残すことが必須です。
| 種類 | 内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| 口頭での贈与 | 話し合いだけで成立 | 証拠が残らず、トラブルになりやすい |
| 書面での贈与(贈与契約書) | 贈与者と受贈者が署名・押印 | 税務上も明確化でき、課税の対象が判断しやすい |
私、横手は実務上、贈与契約書を作成する際には「贈与の目的」「贈与の時期」「贈与する財産の詳細」を具体的に記載し、できれば公正証書化することをおすすめしています。
これにより、贈与の事実が明確になり、将来的な使い込みや相続時の不公平といった疑念を防ぐことができます。
参考:親の貯金を安全に使うには?使い込みでなく計画的な贈与や信託の方法
生前贈与の主なメリット
生前贈与の最大のメリットは、「親が元気なうちに意思を反映できる」ことです。
特に、次のような点で多くのご家庭にメリットがあります。
相続対策としての財産移転
生前に少しずつ財産を渡しておくことで、相続財産を減らし、将来の相続税の負担を軽減できます。
介護や生活支援への報酬としての公平化
特定の子どもが親の介護や生活を支えている場合、親が生前に一定の財産を渡すことで感謝の形にできます。
親の意思を確実に伝えられる
亡くなった後に「遺言書の解釈をめぐる争い」が起きる前に、親が直接伝えることで誤解を減らせます。
私、横手は現場で、「親がありがとうの気持ちを形にして伝えられたことで、家族関係がむしろ円満になった」という事例を何度も見てきました。
生前贈与のデメリットと注意点
一方で、生前贈与には慎重に考えるべきリスクも存在します。
贈与税が発生する
年間110万円を超える贈与には、贈与税が課税されます。特に不動産の贈与は登記費用や不動産取得税なども伴います。
親の老後資金が不足する可能性
贈与した後に親が病気や介護で多額の費用を必要とした場合、「渡しすぎてしまった」と後悔するケースもあります。
兄弟間トラブルの火種になる
一部の子どもだけが贈与を受けると、他の兄弟から「不公平だ」と不満が出ることがあります。特に遺産分割時に「特別受益」として調整が求められることもあるため、家族間での共有と説明が不可欠です。
私、横手は「贈与とは財産を減らすことではなく、関係を残すこと」だと考えています。
目先の節税や整理だけでなく、家族の将来を見据えた設計が大切です。
贈与は「渡す」、家族信託は「託す」という違いがある
生前贈与と混同されやすいのが「家族信託」です。
両者の目的は似ていますが、贈与は所有権を移すのに対し、信託は管理を任せるという点で根本的に異なります。
| 項目 | 生前贈与 | 家族信託 |
|---|---|---|
| 財産の帰属 | 受贈者に完全に移転 | 受託者が管理・運用し、最終的な受益者が利益を得る |
| 税金 | 贈与税が発生 | 信託設定時には原則課税なし(贈与ではないため) |
| 管理の柔軟性 | 一度渡したら取り戻せない | 信託契約の内容に基づき、管理・変更が可能 |
| 適しているケース | 明確に譲りたい財産がある場合 | 認知症など将来の財産管理を見据える場合 |
私、横手はこの二つを「どちらが良い・悪い」ではなく、「目的によって使い分けるべき」と考えています。
たとえば、「子に自宅を相続させたい」なら贈与が有効ですが、「老後の生活費も管理してほしい」なら家族信託のほうが実務的です。
全てを生前に贈与しなくてはいけないというわけではありませんし、全ての財産を家族信託の対象にしなくてはいけないということもありません。
どんな人でも認知症になるリスクがあり、認知症になると生前贈与も家族信託も手続きができなくなってしまうので、ひとつひとつの財産について、贈与するのか信託として託すのかよく考えて契約書という形で明文化しておくことを私はお勧めしています。契約書を作ると言っても、ちゃんとポイントを押さえた契約書になっていないと、実際に信託された資産を運用しようとしたときにできないということも起きてしまいます。
私はたくさんのケースを扱ってきましたので、そのようなリスクを防ぐためにも私にご相談ください。
不動産を贈与するときの注意点
特に不動産の贈与は、金銭以上に慎重さが求められます。
登記の移転には司法書士手続きが必要で、固定資産税評価額に応じた贈与税・登録免許税・不動産取得税が課されます。
また、名義を完全に子へ移すと、親がその家に住み続ける場合でも「贈与した家に無償で住んでいる」とみなされ、贈与税の課税対象とされるリスクもあります。 そのため、私は実務上、不動産の贈与を検討する際には「信託契約に組み入れる」か、あるいは「居住権を設定する」などの方法で親の生活の安全を守る設計を行います。
生前贈与は「想いを伝える契約」だが、仕組みは慎重に
生前贈与は、単なる財産移転ではなく、「親の意思を形にする契約」です。
しかし、税金や家族間の公平性、老後資金の確保といった問題を見落とすと、せっかくの贈与がトラブルの火種にもなりかねません。
私、横手はこうお伝えしています。
「贈与とは、渡すだけでなく、どう生かされるかを設計すること。」
そのためには、贈与契約・家族信託・遺言をバランスよく組み合わせ、親の想いを安心して次の世代に託せる形にしていくことが大切です。