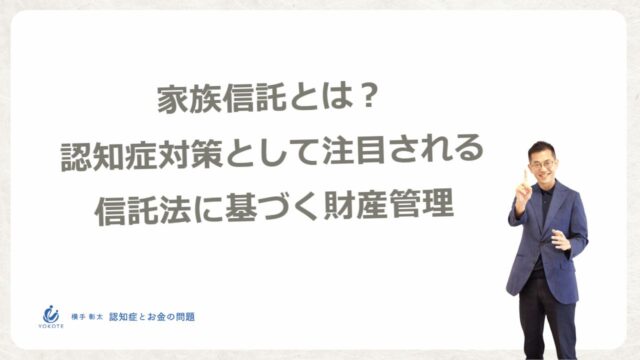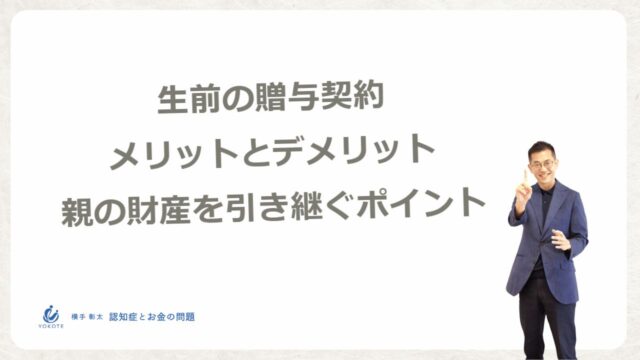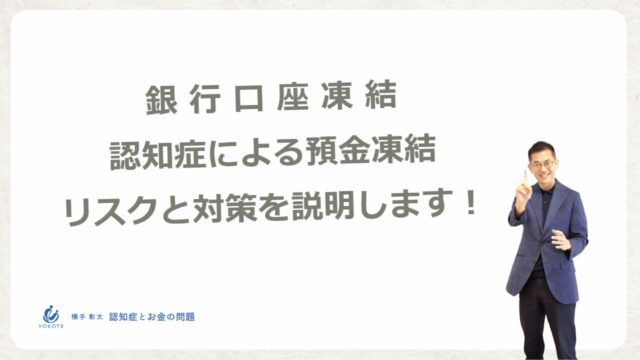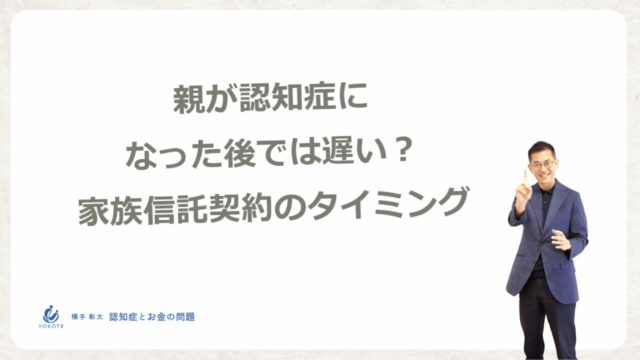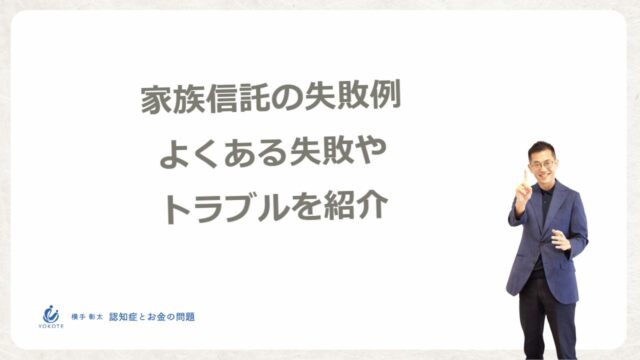家族信託と生前贈与の違いとは?税務面の注意点
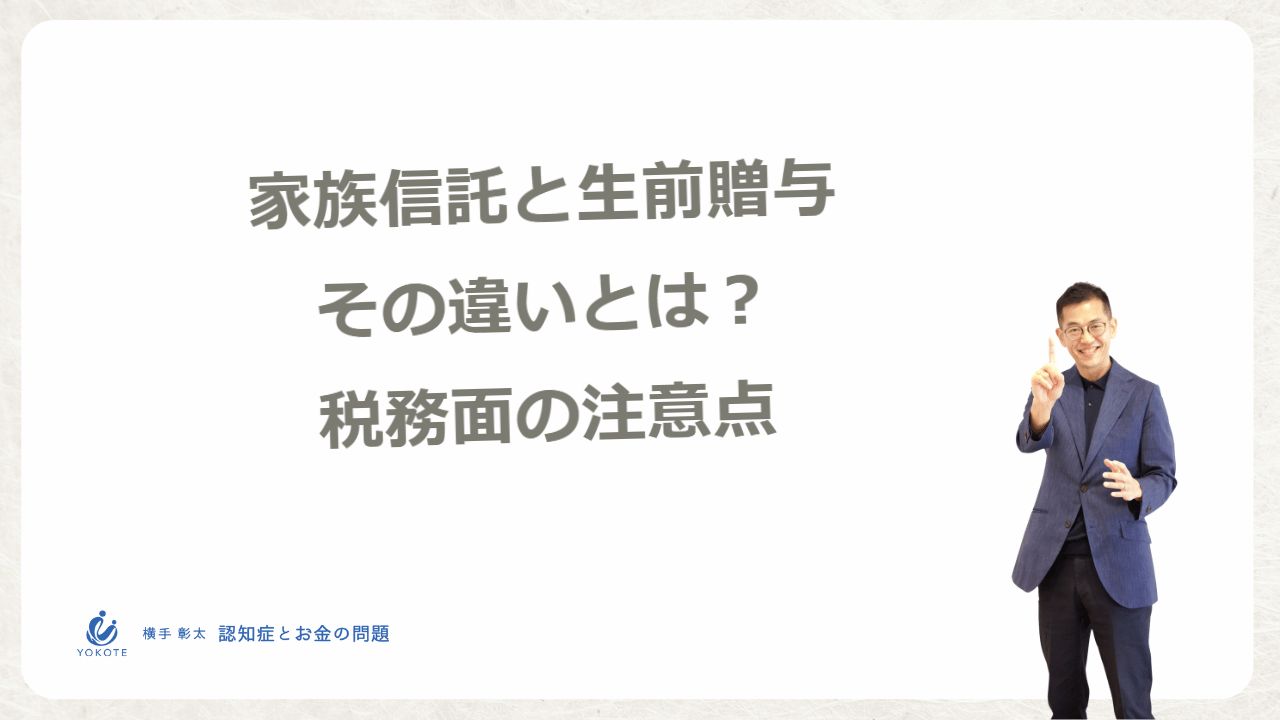
親から子や孫へ財産を渡す方法として「生前贈与」が広く知られていますが、近年注目を集めているのが「家族信託」です。どちらも財産承継の手段ですが、仕組みや税務の扱いは大きく異なります。贈与は所有権を完全に移転するのに対し、家族信託は管理と承継を分けることができ、認知症対策や資産凍結防止に有効です。ただし、契約の設計を誤ると贈与とみなされ課税対象になるリスクもあります。
本記事では、家族信託と生前贈与の違いをわかりやすく整理し、それぞれのメリット・デメリット、税務面での注意点、どのようなケースでどちらを選ぶべきかを専門家の考え方を踏まえて解説します。
この記事の筆者
認知症とお金の専門家・横手彰太。これまでに家族信託の締結サポートは累計350組以上、信託財産総額180億円超を担当してきました。
日本全国67ヶ所の公証役場での手続き実績があり、NHK「クローズアップ現代+」やAERA、プレジデント、日本経済新聞など多数メディアでも紹介されています。セミナー講師としても300回以上登壇し、一般のご家庭から税理士、不動産会社まで幅広い方々にお金と認知症対策について解説してきました。著書に『親が認知症になる前に知っておきたいお金の話』をはじめ計5冊があります。

親が認知症になると、財産管理や相続の問題が一気に複雑化します。
だからこそ、「備えるなら今」が大切です。親に認知症の症状がある場合はすぐに対策しないと後悔しますので無料相談をお申し込みください。家族信託を詳しく学びたい方は2時間以上の濃い内容で解説した特別YouTube動画もご案内していますので、ぜひ最後までご覧ください。
認知症とお金の問題は、本当に重要な問題です。
手遅れになる前に、しっかりと考えて行動しましょう。
家族信託と贈与の基本的な違い
親から子へ財産を引き継ぐ方法として、従来よく用いられてきたのは「贈与」です。贈与は財産を完全に受け渡すもので、名義も実際の所有権も受贈者に移ります。一方、家族信託は財産の「所有権」と「受益権」を分ける仕組みです。親(委託者)が子ども(受託者)に財産の管理を託すものの、利益を受け取る権利は親自身や指定された受益者が持ち続けます。
私はこの違いを「財産を手放す贈与」と「財産を生かし続ける信託」と表現しています。
家族信託とは?
家族信託とは、親など財産を持つ人が、自らの財産の管理や処分を信頼できる家族に託す制度です。信託契約を結ぶことで、銀行口座や不動産が認知症などで凍結されても、受託者が契約に基づいて資産を管理・運用できます。遺言や成年後見制度と異なり、生前から効力を発揮し、相続発生後もスムーズな承継が可能になる点が特徴です。
生前贈与とは?
生前贈与とは、親などが生きているうちに子や孫へ財産を移転する方法です。年間110万円までの基礎控除があり、計画的に行うことで相続税対策にも活用されます。不動産や現金などを贈与すると、名義や所有権は完全に受贈者に移ります。一方で、贈与税や不動産取得税がかかる場合もあり、資産活用や税負担の面で注意が必要です。
家族信託と生前贈与の違い
| 項目 | 家族信託 | 生前贈与 |
|---|---|---|
| 法的根拠 | 信託法 | 民法(贈与契約) |
| 所有権の移転 | 名義は受託者に移るが、受益権は委託者や受益者に残る | 所有権が完全に受贈者へ移転する |
| 利益の享受 | 受益者(親など)が継続して利益を受け取れる | 受贈者(子や孫)が自由に利用できる |
| 認知症対策 | 有効。認知症発症後も受託者が財産管理を継続できる | 効果なし。認知症後は本人名義の財産は凍結される |
| 税務上の扱い | 原則として贈与税は発生しないが、契約設計次第では課税対象になることもある | 年間110万円を超えると贈与税が発生。不動産は取得税や登録免許税も必要 |
| 活用目的 | 認知症対策、資産の承継設計、相続トラブル回避 | 相続税対策、財産の早期移転 |
| 柔軟性 | 契約内容で管理や承継のルールを細かく設定できる | 単純に財産を渡すため、柔軟性は低い |
家族信託と生前贈与、どちらを選ぶべきか?
家族信託と生前贈与は、いずれも親から子へ財産を承継するための有効な手段ですが、その目的やタイミングによって適した選択肢は異なります。
もし「相続税対策」を重視し、少しずつ財産を移して将来の税負担を軽減したいのであれば、生前贈与が有効です。ただし、贈与税や不動産取得税などの負担が伴い、一度移転した財産は親の手元に戻せない点には注意が必要です。
一方で、「認知症対策」を重視し、親が意思能力を失っても財産を活用できるようにしておきたいのであれば、家族信託が適しています。家族信託であれば、銀行口座の凍結や不動産売却の停止といったリスクを回避でき、介護費用や生活資金をスムーズに確保できます。
私横手も強調するように、最も大切なのは「どのような未来を描きたいか」を家族で共有し、それに合った制度を選ぶことです。どちらを選んでも一長一短があり、契約設計や税務の取り扱いを誤ると大きなリスクになります。そのため、専門家の知見を取り入れて最適な方法を判断することが、本人と家族にとって最も安心できる選択につながります。
ケース別のシナリオ表
| 家族の状況・目的 | 適した制度 | 理由 |
|---|---|---|
| 相続税の節税を重視したい | 生前贈与 | 年間110万円の非課税枠を活用し、時間をかけて少しずつ財産を移せるため相続税対策に有効 |
| 認知症による財産凍結を避けたい | 家族信託 | 親が認知症になっても契約に基づき受託者が財産を管理できるため、口座凍結や不動産売却不能のリスクを回避できる |
| 不動産を老後の生活資金に充てたい | 家族信託 | 将来的に売却や賃貸をスムーズに行えるため、介護費用や老人ホーム資金を安定的に確保できる |
| 子や孫に早めに資産を渡したい | 生前贈与 | 教育資金や結婚資金など、必要な時期に合わせて財産を移転でき、生活支援にもつながる |
| 相続トラブルを防ぎたい | 家族信託 | 契約の中で財産の管理・承継ルールを詳細に決められるため、兄弟姉妹間の不公平感を防げる |
税務面の注意点
贈与では、年間110万円を超える贈与は贈与税の対象となります。また、不動産の場合は登録免許税や不動産取得税がかかり、思った以上に負担が大きくなることがあります。
これに対して家族信託は、原則として贈与税は発生せず、相続税評価も委託者に帰属したままとなります。ただし、契約の設計を誤ると贈与とみなされるリスクがあり、課税対象になる可能性も否定できません。
| 項目 | 家族信託 | 生前贈与 |
|---|---|---|
| 贈与税 | 原則として発生しない。受益権が委託者に残るため「所有権の移転」とはみなされない。ただし契約設計が不適切だと贈与と判断され課税されるリスクあり | 年間110万円を超える贈与は贈与税の対象となる。相続税対策として少額贈与を長期間継続するケースが多い |
| 相続税 | 委託者が受益権を持ち続ける場合、相続税評価は委託者に帰属する。信託契約終了時に受益者へ移転すると課税対象になる | 贈与した財産は受贈者に帰属し、原則として相続財産から除外される。ただし相続開始前3年以内の贈与は持ち戻し規定が適用される |
| 不動産取得税・登録免許税 | 信託登記に伴い登録免許税が発生。受託者への移転は原則として不動産取得税は非課税 | 不動産を贈与すると登録免許税や不動産取得税が課税される。税負担が大きくなる場合あり |
| 所得税 | 受益者が得る利益に課税される場合があるが、設計次第で対応可能 | 贈与そのものでは所得税は発生しないが、受贈した財産から収益が生じれば課税対象になる |
| 注意点 | 信託契約の内容次第で課税関係が大きく変わるため、専門家の設計が不可欠 | 贈与税や不動産取得税の負担を見誤ると想定以上の納税義務が発生する可能性がある |
認知症対策としての有効性
贈与は財産を早めに移転することはできますが、親が認知症になった後の財産管理には役立ちません。認知症を発症すると銀行口座は凍結され、不動産の売却や賃貸も不可能になります。家族信託であれば、委託者の意思能力が低下しても契約に基づいて受託者が管理を継続できるため、介護費用や生活資金を安定的に確保できます。これは横手氏が長年の実務経験の中で強調している「家族を守るための仕組み」といえます。
専門家の知見を取り入れる重要性
家族信託は自由度が高い分、契約設計を誤ると想定通りに財産を動かせなくなったり、思わぬ税負担が発生したりする恐れがあります。正しい知識を得たうえで、専門家とともに設計することが本人と家族にとって最も安心できる形につながります。読者の方もまずは家族信託の基本を理解し、信頼できる専門家と相談することで最適な形を見つけることができます。
早めの対応が未来を守る
もし親がすでに軽度認知症の症状を見せている場合、契約が難しくなる可能性があります。公証人や医師の判断で意思能力が不十分とされれば、家族信託は締結できません。そのため、対応は「まだ大丈夫」と思える今の段階が最も適しています。財産管理や信託の選択肢は時間が経てば経つほど狭まってしまいます。もし不安を感じているなら、すぐに無料相談を申し込み、具体的な対策を進めることを強くおすすめします。
まとめ
家族信託と贈与は似ているようで大きく異なる制度です。贈与は財産を一度に移す方法ですが、家族信託は財産を「管理しながら活かす」仕組みであり、認知症対策において非常に有効です。ただし、契約設計や税務の扱いには専門的な知識が必要となります。横手彰太氏が強調するように、知識を身につけ、早めに正しい準備を始めることが、本人と家族を守る確実な方法です。