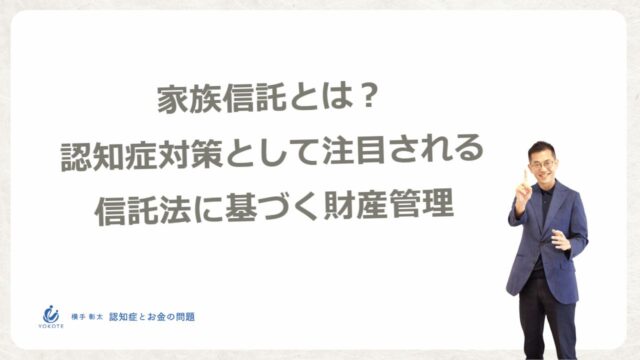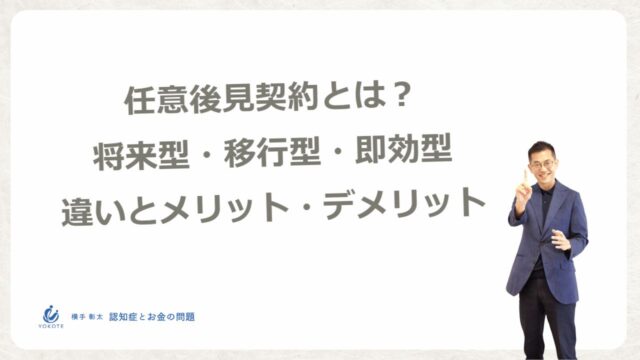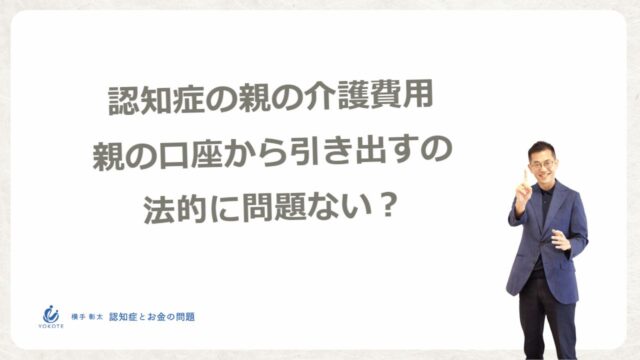遺言書は勝手に開封禁止!認知症で生存中の財産管理の備えはできてる?
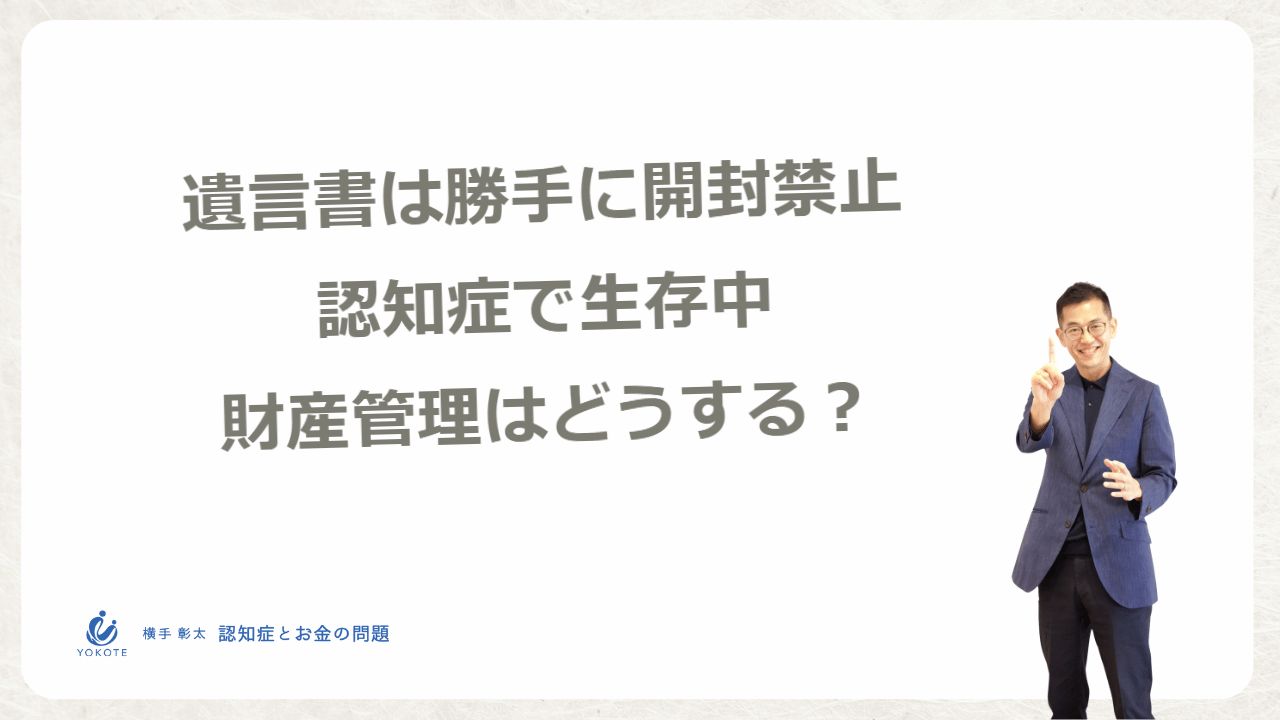
「うちの親は遺言書を書いているから大丈夫」――そう思って安心していませんか?
私、横手はこれまで多くの相談を受けてきましたが、遺言書があっても認知症になった途端にお金が動かせなくなったというご家庭が少なくありません。
遺言書は、本人が亡くなった後に効力を発揮するものであり、生きている間の財産管理には一切使えません。
しかも、家庭裁判所の検認を受ける前に勝手に開封することは法律で禁じられています。
では、もし親が認知症になり、判断能力を失ったら――
生活費や老人ホームの入居費、不動産の処分はどうすればよいのでしょうか。
この記事では、家族信託コンサルタントの私・横手彰太が、遺言書の限界と、生前の財産管理を整えるための具体的な備えについて、専門的な立場からわかりやすく解説します。
この記事の筆者
認知症とお金の専門家・横手彰太。これまでに家族信託の締結サポートは累計350組以上、信託財産総額180億円超を担当してきました。
日本全国67ヶ所の公証役場での手続き実績があり、NHK「クローズアップ現代+」やAERA、プレジデント、日本経済新聞など多数メディアでも紹介されています。セミナー講師としても300回以上登壇し、一般のご家庭から税理士、不動産会社まで幅広い方々にお金と認知症対策について解説してきました。著書に『親が認知症になる前に知っておきたいお金の話』をはじめ計5冊があります。

親が認知症になると、財産管理や相続の問題が一気に複雑化します。
だからこそ、「備えるなら今」が大切です。親に認知症の症状がある場合はすぐに対策しないと後悔しますので無料相談をお申し込みください。家族信託を詳しく学びたい方は2時間以上の濃い内容で解説した特別YouTube動画もご案内していますので、ぜひ最後までご覧ください。
認知症とお金の問題は、本当に重要な問題です。
手遅れになる前に、しっかりと考えて行動しましょう。
「遺言書があるから大丈夫」と思っていませんか?
私、横手は日々多くのご家族から相談を受けていますが、「うちの親は遺言書を書いているから大丈夫」と安心されている方が少なくありません。
しかし、実はこの言葉の裏にこそ、大きな誤解が潜んでいます。
遺言書は、本人が亡くなった後に効力を発するものであり、生きている間の財産管理には一切使えません。
そして、遺言書を見つけたとしても、勝手に開封することは法律で禁じられています。
民法第1004条では、「遺言書は家庭裁判所の検認を受けなければ開封してはならない」と明記されており、勝手に開けてしまうと過料(罰金のような行政罰)が科せられることもあります。
つまり、遺言書があるだけでは、生前の生活資金・介護費用・不動産管理など、本人がまだ生きている間の経済的問題は何ひとつ解決できないのです。
遺言書の効力が及ぶのは「死後」だけ
遺言書は本人が亡くなった後、相続人の間で財産をどう分けるかを指定するための書類です。
一方で、本人が認知症などで判断能力を失い、契約や出金ができなくなった時点では、遺言書はまったく効力を発揮しません。
たとえば、本人名義の銀行口座から生活費を引き出したり、自宅を売却して老人ホームの費用に充てたりすることは、家族であってもできません。
銀行は、本人の意思確認が取れない場合、法律上のトラブルを防ぐために口座を凍結します。
不動産の売却も同様に、登記に必要な「本人の署名・押印・意思確認」ができないため、売ることができません。
私、横手は現場で「遺言書はあるけれど、認知症になってから生活費が出せなくなった」というご家族に何度も出会ってきました。
このようなケースでは、遺言書の存在がむしろ安心感を生み、結果として「生前の備え」が後回しになってしまっていたのです。
認知症になると「財産はあるのに使えない」現実が待っている
認知症の怖さは、記憶を失うことだけではありません。
法律上、「契約行為ができない人」とみなされることで、あらゆる資産の動きが止まってしまうことにあります。
預金、不動産、株式、年金、すべての手続きに共通して求められるのは「本人の意思確認」です。
判断能力が失われた瞬間から、本人がどれだけお金を持っていても「事実上使えなくなる」。
私、横手はこれを「資産が凍る瞬間」と呼んでいます。
多くのご家族がこの現実に直面して初めて、「遺言書だけでは足りなかった」と気づきます。
しかし、認知症が進行したあとでは、信託契約や任意後見契約などの手続きはもうできません。
つまり、「備え」は元気なうちにしかできないのです。
生前の財産管理を可能にする「家族信託」という選択肢
では、どうすればよいのでしょうか。
私、横手が最も有効だと考えているのが、「家族信託」という制度です。
家族信託とは、本人(委託者)が信頼できる家族(受託者)に財産の管理・運用・処分を託す契約のことです。
この契約を結んでおけば、親が認知症になったとしても、信託された財産は家族が管理・運用を続けることができます。
たとえば、自宅を信託しておけば、施設入居時に売却して費用に充てることができます。
預金を信託口口座に預けておけば、介護費や医療費を子どもが代理で支出できます。
つまり、家族信託は「本人が生きている間のお金の流れを止めない」ための仕組みなのです。
この仕組みの大きな特徴は、家庭裁判所の関与が不要である点にあります。
成年後見制度のように報告義務や監督人の費用がかからず、家族が自分たちの判断で柔軟に資産を守ることができます。
家族信託と遺言書は「セット」で考える
家族信託は生前の財産管理を目的とし、遺言書は死後の財産分配を目的とします。
この二つを組み合わせることで、「生前も死後も安心」という理想的な資産設計が実現します。
たとえば、信託契約の中で「本人の死後は誰に財産を渡すか」を定めておけば、実質的に遺言と同様の効果を持たせることもできます。
それでも、細かな遺産分割や想定外の事態に備えるために、家族信託と公正証書遺言を併用しておくことを私は推奨しています。
実際、私が支援しているご家庭でも、「遺言書と家族信託を併用しておいてよかった」という声が圧倒的に多く聞かれます。
一方で、遺言だけに頼っていたケースでは、「認知症の進行でお金が動かせなくなった」「相続の前に介護費が払えなくなった」といった問題が後を絶ちません。
「遺言書の前に、生前の備え」を
私、横手は「遺言書を書く前に、生きている間をどう守るか」を考えることが何より大切だとお伝えしています。
遺言は「終わりの備え」ですが、家族信託や任意後見契約は「生きるための備え」です。
親が元気なうちに、「もし認知症になったら、生活費はどうする?」「不動産はどう管理する?」という話し合いをすることが、最良の相続対策になります。
遺言書は重要です。しかし、それは人生の最終章を整えるためのもの。
その前に訪れる“老後の現実”を見据え、どのように財産を活かし、誰が支えていくのか――
それを形にするのが、生前の財産管理の仕組みづくりです。
遺言より先に「信託を」
遺言書は、勝手に開封してはいけません。
そして、遺言書があっても、本人が生きている間の資金管理や不動産の活用には使えません。
認知症が進んでからでは遅く、契約も決定もできなくなります。
だからこそ、遺言書を書く前に「生前の財産管理」を整えることが必要です。
私、横手は現場で何度も、「もっと早く知っていれば…」という後悔の言葉を聞いてきました。
遺言書だけでは守れない生きている間の安心――
その答えが、家族信託にあるのです。